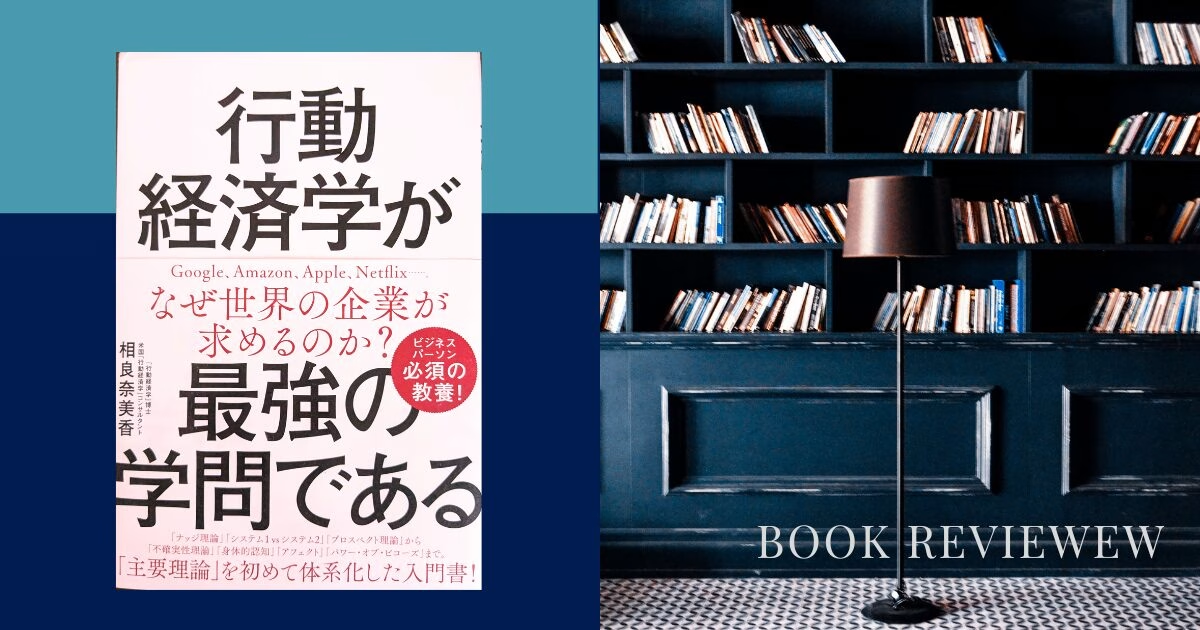本の概要
- タイトル:行動経済学が最強の学問である
- 著者等:相良奈美香
- 出版社:SBクリエイティブ
本書の構成は次の通りです。
◆プロローグ いま世界のビジネスエリートがこぞって学ぶのが「行動経済学」
◆序 章 本書といわゆる「行動経済学入門」の違い
・そもそも行動経済学は「なぜ生まれた」のか?
・「従来の行動経済学」は体系化されていない
・行動経済学を「初めて整理・体系化」した入門書
◆第1章 認知のクセ――脳の「認知のクセ」が人の意思決定に影響する
・認知のクセを生む「大元」は何か?
・システム1が「さらなる認知のクセ」を生み出す
・「五感」も認知のクセになる
・「時間」も認知のクセになる
◆第2章 状況――置かれた「状況」が人の意思決定に影響する
・人は状況に「決定させられている」
・「多すぎる情報」が人の判断を狂わせる
・「多すぎる選択肢」でどれも選べなくなる
・「何」を「どう」提示するかで人の判断が変わる
・「いつ」を変えるだけで人の判断が変わる
◆第3章 感情――その時の「感情」が人の意思決定に影響する
・そもそも「感情」とは何か?
・「ポジティブな感情」は人の判断にどう影響するか?
・「ネガティブな感情」は人の判断にどう影響するか?
・感情が「お金の使い方」にも影響を与える
・「コントロール感」も人の判断に影響を与える
・「不確実性」も人の判断に影響を与える
◆エピローグ あなたの「日常を取り巻く」行動経済学
・「自己理解・他者理解」と行動経済学
・「サステナビリティ」と行動経済学
・「DEI」と行動経済学
学びと共感
「なぜ人はそう行動するのか?」
従来の経済学では、人は合理的な存在と考えるが、人は必ずしも合理的ではなく非合理な存在という認識にたって、人間の非合理な意志決定のメカニズムを解明する学問が行動経済学だと著者は指摘している(経済学と心理学が融合したようなもの)。
そして、人がついつい「非合理な意思決定」をしてしまうメカニズムには大きく「認知のクセ」「状況」「感情」の3つの要因があると述べられています。
本書は行動経済学の初学者向けに、その「認知のクセ」「状況」「感情」の3つをそれぞれで章立てて、具体例を交えながらとても分かりやすく説明されています。私自身も読んでいて「そうそう、こういうことってあるよね」と共感しまくりでした。
「認知のクセ」の章では、直感で即断するシステム1と、熟考するシステム2の二系統に関する話題、「状況」の章では、人間の意識が向くのは「今」なので、今のことについては現実的かつ具体的に考える。逆に時間が先になるにつれ、思考はイメージ優先(=抽象的)になっていくという認知のクセ(解釈レベル理論)や、フレーミング効果・アンカリング効果・自律性バイアスを活用した仕事の依頼方法・「疲れると現状維持を選ぶ」という示唆など、実務に即活かせる理論が多数紹介されています。
「感情」の章では、強いエモーションではなく淡い感情=アフェクトが日常の意思決定に大きな影響を与えることが説明されています。合理的な資料を出すだけでなく、相手のアフェクトがポジティブかネガティブかを知ってアプローチした方が効果的だと説きます。
エピローグでさえも、自己理解・他者理解の3つの切り口が説明されており、多くの学びと気づきがあります。
日本人として数少ない行動経済学の博士(オレゴン大学ビジネススクール博士課程修了)で、行動経済学コンサルタントの著者がまとめた力作は、とてもとても知的好奇心をくすぐられる、もっと行動経済学を深く知りたいと感じる一冊です。
ビジネスパーソンは全員読むべきでしょう!
超お勧めです、ぜひ手に取ってみてください!!