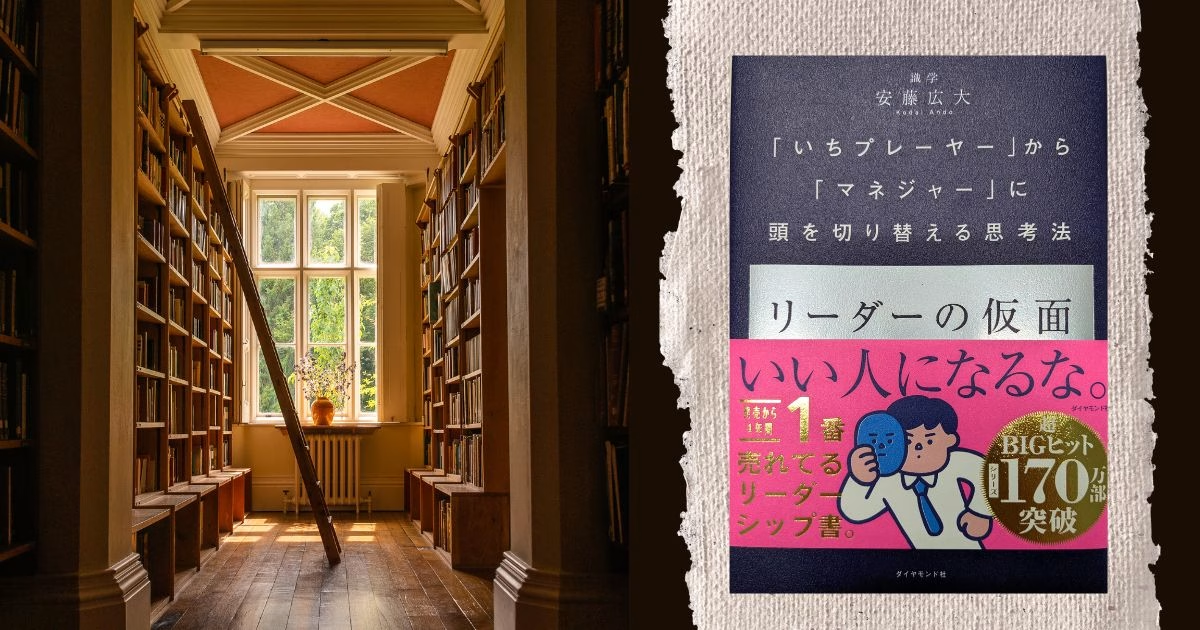概要
- タイトル:リーダーの仮面
- 著者等:安藤広大
- 出版社:ダイヤモンド社
本書の構成は次の通りです。
◆はじめに なぜ、「リーダーの言動」が大事なのか?
- 優秀な人ほど犯す2つの「失敗」
- リーダータイプは才能なのか?
- 「5つのポイント」以外はスルーしていい
- その「ひと言」は後から効いてくるか
- 「仮面」はあなたを守ってくれる
- なぜ、会社は「変わらない」のか
◆序章 リーダーの仮面をかぶるための準備 ── 「錯覚」の話
- 感情的なリーダーが犯した失敗
- いかなるときも「個人的な感情」を横に置く
- 「5つのポイント」だけで別人のように変われる
- 序章の実践 プレーヤーから頭を切り替える質問
◆第1章 安心して信号を渡らせよ ── 「ルール」の思考法
- 「自由にしていい」はストレスになる
- ルールは「誰でも守れる」が絶対条件
- 「リーダー失格」の行動とは何か
- 「ダメなルール」はみんなを混乱させる
- 第1章の実践 「姿勢のルール設定」をやってみる
◆第2章 部下とは迷わず距離をとれ ── 「位置」の思考法
- ピラミッド組織を再評価しよう
- 位置によって「見える景色」が異なる
- 「お願い」ではなく「言い切り」で任せる
- ストレスのない「正しいほうれんそう」をしているか
- 「これパワハラ?」問題を乗り越える
- リモートによって「あいた距離」を維持しよう
- 第2章の実践 「正しいほうれんそう」をやってみる
◆第3章 大きなマンモスを狩りに行かせる ── 「利益」の思考法
- 部下の「タテマエ」を本気にするな
- どこまで行っても「組織あっての個人」
- 「集団の利益」から「個人の利益」が生まれる
- リーダーは「恐怖」の感情を逆に利用する
- 事実だけを拾い、「言い訳の余地」をなくしていく
- 健全なる「競争状態」をつくる
- 第3章の実践 「言い訳スルー」をやってみる
◆第4章 褒められて伸びるタイプを生み出すな ── 「結果」の思考法
- 他者の「評価」からは誰も逃げられない
- リーダーは「プロセス」を評価してはいけない
- 「いい返事」に惑わされるな
- リーダーがやるべき「点と点」の管理術
- 「結果」を元に次の目標を詰める
- 第4章の実践 「点と点の目標設定」をやってみる
◆第5章 先頭の鳥が群れを引っ張っていく ── 「成長」の思考法
- 「不足を埋める」から成長が生まれる
- チームが成長するとき、必ず起きていること
- 「変わった気になる」を徹底的になくしていく
- 第5章の実践 「とにかく一度行動させる」をやってみる
◆終章 リーダーの素顔
- もっとも「人間」を追求したマネジメント
- リーダーは「逃げ切ろう」とするな
- 「おわりに」に代えて ── 私たちの成長の話
『リーダーの仮面』—「好かれる」より「機能する」リーダーへ
本書は、株式会社識学 代表取締役社長の安藤広大が執筆されたマネジメントに関するノウハウ本です。
リーダーが個人の感情や好悪から距離を置き、「仮面」を被って組織を機能させるための原則を提示する一冊で、識学のフレームに基づき、リーダーの役割を「部下を成長させ、チームの成果を最大化すること」と定義し、具体的な行動規範へと落とし込む提案が続きます。
本書の主張(核となる5つのフォーカス)
- ルール
場の空気ではなく、誰が何をいつまでにやるかを言語化し、全員に明文化して伝える。主語は必ず「自分」。例:「会議は5分前集合」をメールや共有ファイルで明文化し、齟齬の責任は上司が負う。 - 位置
対等ではなく上下の関係でコミュニケーションする。1on1で「寄り添いすぎる」姿勢は決定権の所在を曖昧にし、成長を止める。期日と指示を言い切り、定期報告を受ける。 - 利益
人間的魅力ではなく、組織の利益に資するかで動かす。顧客満足を追うあまり、自社の利益を損なう施策(例:24時間対応)は長期的に組織を弱める。 - 結果
プロセスは評価せず結果で評価。冒頭に目標を明確化し、最後に結果で評価する。上司が相談に乗るのは「権限外の決定」と「決定権の範囲に迷うとき」だけ。 - 成長
「結果」と「評価」のギャップを埋めていくことが成長。知識は経験と結びついて初めて血肉化するため、まずやらせ、プロセスには口を出しすぎない。
印象に残る論点
- 組織>個人の順番を徹底
「言ったもの勝ち」になった瞬間、組織は終わる。
嫌なら辞めてもらって構わないが、残るならルールに従うべきという毅然さ。 - 距離のマネジメント
「飲みニケーションは終わった」。業務の指摘は業務中に。
仲良しは役割ではなく、健全な距離が機能を生む。 - 「適材適所」を否定
まず役割があり、個がそこに適応する。
組織に個を合わせる順序が、成長と競争を生むという逆説。 - 「頑張る理由を用意しない」
指示の実行は当然。意味付けや情緒で動機づけを上塗りしないのが識学流。 - リーダーの自制としての仮面
説教したくなる衝動を抑え、競争が起きる設計と評価軸でチームを前に進める。
実務への示唆
- ルールは主語「私」で明文化し、全員が見える場所に置く(いつでも確認できるように)。
- すべての指示に期限と報告方法をセットにする。
- 1on1はやめる。
- 評価は目標と実績の二点で行い、プロセス評価をやめる。
- 顧客対応は「自社の利益」を軸に線引きする。
(間違って顧客利益の最大化にならないように) - チーム内に健全な競争が起こる設計(目標と可視化)を用意する。
- 部下と必要な距離を保ち、注意はその場で、感情ではなくルールで伝える。
総評
1on1は上司と部下の位置関係を間違えたダメな方法だと言い切っていたり、プロセスを評価しないという主張など、他のマネジメントに関する書籍と一線を画する主張が随所にあります。
マネジメントは、部下に寄り添うという文脈で語られることも多いが、そういった風潮に違和感を感じている方にとって最良の気づきが得られるのではないでしょうか。
リーダーの仕事を「好かれること」から「機能させること」へと切り替えるトリガーになる一冊。
これは決して人間味を捨てろという話ではなく、人間味を「仮面」の内側にしまい、組織を前進させるために外側はルールと位置と結果で固め徹底するという主張だと感じました。
組織の利益に貢献し続ける人が最後に強い、という現実を直視させる点で、リーダーが果たさねばならない根源的な役割を思い出させてくれる内容になっています。
好かれたいリーダー像から抜け出せずに悩む方にお勧めしたい一冊です。