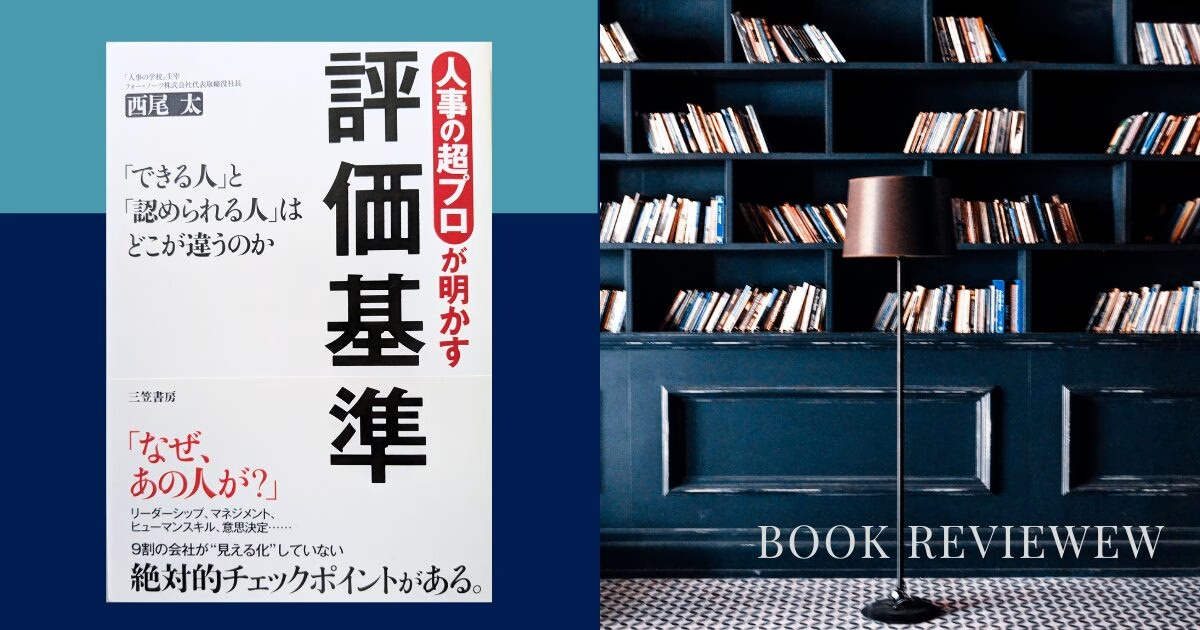概要
- タイトル:人事の超プロが明かす評価基準
- 著者等:西尾 太
- 出版社:三笠書房
リンク
本書の構成は次の通りです。
◆はじめに 自分の会社の「人事評価」の基準を知っていますか?
◆第1章 なぜあの人は「評価されるのか」「されないのか」―評価する側、される側の“見えない壁”
◆第2章 「人が大きく成長する制度」―成果主義、相対評価、目標管理制度…あなたの会社は、大丈夫か?
◆第3章 何が評価を決めるのか?―どんな企業にも通用する指標「影響力」とは
◆第4章 絶対的、評価基準「45のコンピテンシー」―「評価に値する行動」を全公開
◆第5章 評価ポイントは年齢によっても変化する―年齢による「周囲の期待の変化」をつかむ
◆第6章 これから待ち受ける「4つの選択肢」―人生勝利の「働き方」と、そこへの最短のルート
◆おわりに 人生を選ぶ自由と力をあなたに
印象に残る論点
本書は、人事評価を処遇決定のためだけでなく、社員の成長と業績向上を促す仕組みとして設計・運用する視点を整理した一冊です。要点は、評価基準の見える化と、日々の運用に重心を置くアプローチにあります。
<主な内容>
- 評価の目的の定義
評価は「人を裁く」ものではなく、良い点は認め、不足は改善につなげる育成プロセス。基準を明文化することで、社員は目標と努力の方向を掴み、評価者も一貫した判断がしやすくなります。 - 絶対評価を推奨
相対評価は分布調整のために達成者の評価が下がるなどの不公平感を生みやすく、制度への信頼を損なう。そして、基準に照らして評価する絶対評価が望ましいとと指摘します。
実現の難しさは感じますが、その主張は私自身も大いに共感するところです。 - 役割期待の明確化
課長には「目標達成」、部長には「戦略策定と目標設定」を求めるなど、役職ごとの期待を明示。現状維持は評価しないという基準もはっきり示すことが重要です。 - 設計より運用
制度そのものより、基準の粒度、目標設定、面談・フィードバックなどの運用を整えることが効果に直結すると説きます。基準が粗いと主観が入りやすく、評価のばらつきが生じます。人事の実務経験がある方の多くが共感されるのではないでしょうか。 - マネジメントの基本行動
部下の状況把握、声かけ・相談対応、キャリアの理解、称賛と改善指摘、強み・弱みへの働きかけなど、日常の関わりが評価と育成の質を左右します。 - 影響力=提供価値
評価の核は組織への影響度。売上やイノベーションはもちろん、管理部門でも工数削減、品質向上、リスク低減などを数値で可視化できます。 - 45のコンピテンシー
これが本書のポイントです。行動特性を言語化した評価・育成の基盤として提示されています。人事だけでなく管理職の実務でも参照しやすく、評価する立場の方も評価される立場の方も参考にできるでしょう。 - 目標の明文化と計画
目標を紙に書き、達成計画まで落とし込み、常に参照できる形にする重要性を、収入比較を交えながら解説されています。
実践ポイント
- 役割と期待の見える化: 「課長=達成」「部長=戦略・目標設定」と「現状維持は評価しない」を明文化。
- 絶対評価とKPI: 影響力=提供価値をKPIに翻訳し、基準に沿って評価・面談を実施。
- フィードバックの仕組み化: 面談頻度・記録・行動支援を標準化し、45のコンピテンシーを共通言語にする。
総評
総じて、本書は評価の理念と現場運用をつなぐ実務的な指針を提供しており、人事担当者はもちろん、評価に関わる管理職にも有用です。評価を落ち着いて機能させるための基本事項が、過不足なく整理されています。
また、オーナー経営者の独断が評価を左右しないよう、制度・運用で恣意性を抑える必要性にも触れられています。中堅・中小企業のオーナー経営者の方に、是非読んでいただきたい本でもあります。
2015年に発売された本ですし、はやりのジョブ型なんて言葉は全く出てきません。
ですが本書の内容は、まだまだ現役です。むしろ、今だから味があるとさえ思えます。
とてもお勧めできる一冊です。
リンク