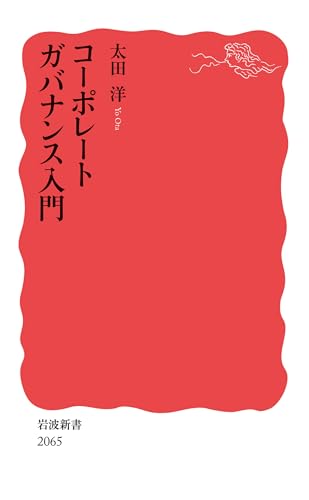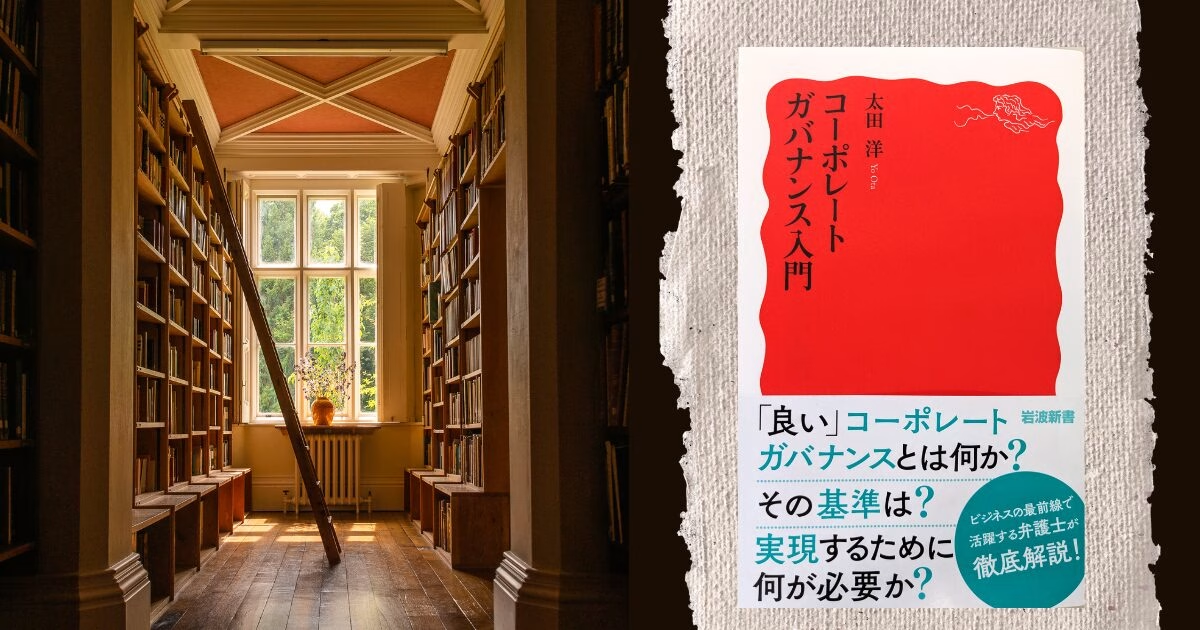概要
- タイトル:コーポレートガバナンス入門
- 著者等:太田洋
- 出版社:岩波新書
リンク
本書の構成は次の通りです。
目次
まえがき
◆第一章 混迷する「コーポレートガバナンス」論
◆第二章 コーポレートガバナンスの目的と企業価値
◆第三章 「良い」コーポレートガバナンスとはどのようなものなのか
◆第四章 コーポレートガバナンスのための「仕組み」
◆第五章 コーポレートガバナンス改革の歴史
◆第六章 「器」としての企業統治機構の設計――米英独仏の場合
◆第七章 「器」としての企業統治機構の設計――日本の場合
◆第八章 コーポレートガバナンスの現在地とその行方
主な参考文献
あとがき
印象に残る論点
- コーポレートガバナンスとは、本来的には会社経営者に対して「規律付け」をするための制度的な担保及び具体的な制度運用の総体を意味するものである。「統治」の語感に引きずられるべきではない。決して会社を締め付けるためのものではない。
- 多数の株主を擁し、所有と経営とが分離した近代的な大企業においては、経営者は株主の利益から離れて、自分自身の利益を追求するようになるため、経営者の「規律付け」が一層重要になる。
- コーポレートガバナンスの目的は「従業員、顧客、取引先、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーと適切に協働しつつ、株主に対する受託責任・説明責任を果たし、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ること」である。
- また、短期的に企業価値向上に資する行為と、中長期的に企業価値向上に資する行為が必ずしも一致しない場面もありえるため、コーポレートガバナンスの目的は「中長期的な」企業価値向上と捉えるべきであるとも説明する。
- 短期重視・中長期重視というように株主の利害は一様ではない。米国では、短期的な利益を極大化するために機会主義的に行動するアクティビストと、機関投資家の大部分を占めるパッシブ投資家株主および株主以外の従業員その他のステークホルダーとの利害相反に伴うコスト・弊害が「水平的エージェンシーコスト」と呼ばれるようになってきている。このエージェンシーコストを最小化することが、コーポレートガバナンス問題の核心である。
※株主と取締役の利害相反に伴うコスト・弊害を垂直的エージェンシーコストと呼ぶのに対比した表現
※代理人たるエージェント(経営陣)が、必ずしも依頼者たる株主の意向に従って職務を遂行するとは限らない。代理人は自分の報酬を極大化したい、自分の地位を守りたいという固有の利害を持っている。この非効率性を「エージェンシーコスト」と呼ぶ。 - 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が実現できているか否か?
- 良いコーポレートがバンスとは、税引き後WACCを超えるROICを持続的かつ中長期的に上回っているかという尺度が第一義の見方になる。
実務への示唆
- 2023年3月、東証は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の要請」を行った。これは、プライム市場・スタンダード市場の全上場会社を対象としている。
東証の発表によると、2025年4月時点で、プライム上場企業においては87%、スタンダード上場企業においては39%が開示対応済となっている一方で、企業でコーポレートガバナンスの担当者が、どれだけ自社の開示の中身を理解されているかは別問題か?
本書は「ガバナンス」と「企業価値の評価方法」が密接に結びついていると改めて気づかせてくれる。自社の資本コストについて深掘りしてみる機会になるのではないだろうか。 - 取締役会の監督の結果を人事に反映する。そのために、独立性の高い指名・報酬委員会を実効化し、目標—評価—報酬/選解任の連動を明確に設計・運用する。
特に指名(人事権)の適切な行使は決定的に重要でしょう。
取締役は会社人生におけるアガリのポジションではなく経営者なのですから、何ら成果のない取締役には退場いただくような制度設計と運用ができるかがガバナンスの要諦です。 - 統治形態の見直し:監査等委員会設置会社や任意(リスク/テクノロジー/ファイナンス)委員会の活用でモニタリング解像度を向上。ただし、指名委員会等設置会社に関しては制度の見直しが進行中であり、この見直しの帰結(法改正)を待ってから。
総評
- 「企業が選ぶ弁護士ランキング」で、企業法務全般(会社法)分野において3年連続で首位を獲得した著者が執筆された本書は、現在の日本におけるガバナンスについて述べるだけでなく、欧米との比較やその歴史についても説明されている点が特徴的です。今に至るまでの経緯とコーポレートガバナンスに関する全般的な理解を深めるうえで、とても有効だと感じました。
- タイトルに入門とありますが、決して入門レベルに留まっている内容ではありません(書きぶりの影響もあるかもしれませんが)。本書の出版記念講演も拝聴した際、入門とあるが入門レベルではないという声が多いと、太田先生も行っておられました。私もそういった読者の感じ方と同じです(笑)
- 執行役員制度は、法律に裏付けされた制度ではありませんが、太田先生には執行役員制度に関しても本書と同じような目線で執筆いただけると、実務家にとって有意義なものになるように思います。もし機会があれば、是非お願いしたいです。
- これからコーポレートガバナンスを勉強しようという方にとっても役立つ内容ですが、ガバナンスの実務に携わり一定の前提知識を持たれている方や企業の法務部門の方、そして経営者にとっても学びがある内容になっています。