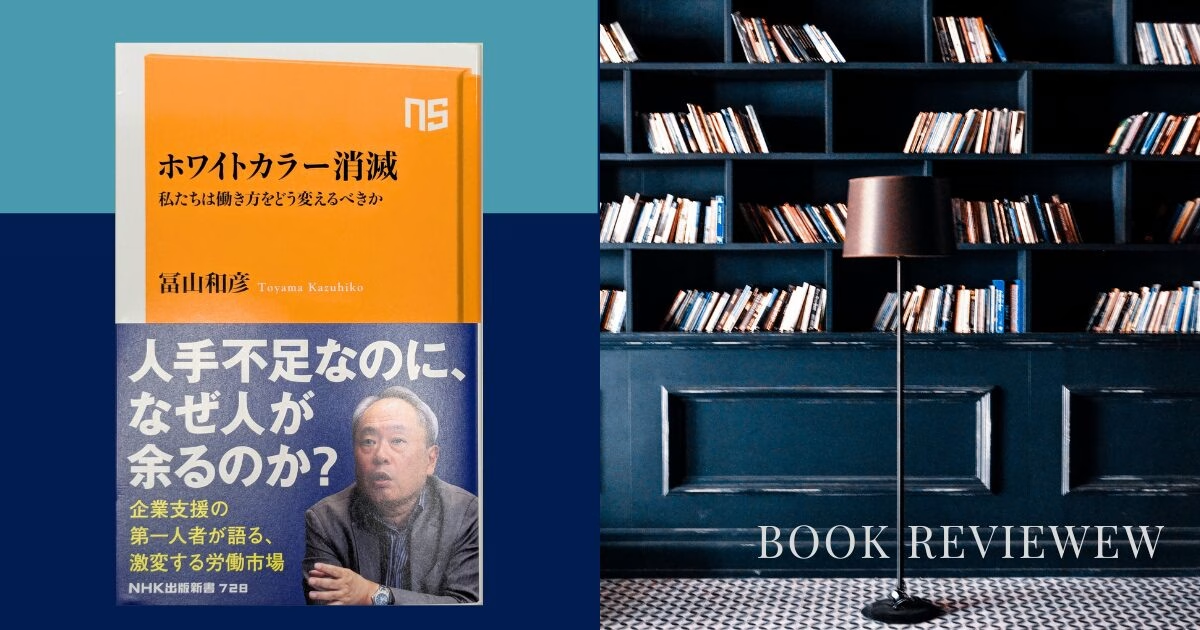概要
- タイトル:ホワイトカラー消滅
- 著者等:冨山和彦
- 出版社:NHK出版新書
リンク
本書の構成は次の通りです。
目次
序章 労働力消滅、ふたたび
第1章 グローバル企業は劇的に変わらざるを得ない
第2章 ローカル経済で確実に進む「人手不足クライシス」
第3章 エッセンシャルワーカーを「アドバンスト」にする
第4章 悩めるホワイトカラーとその予備軍への処方箋
第5章 日本再生への20の提言
印象に残った論点
- IGPIグループ会長で、日本共創プラットフォーム代表取締役社長の著者が執筆された本書の主張はシンプルで一貫しています。
日本経済を危機から救う道筋は、付加価値労働生産性を上げることに尽きる、という点です。労働力供給に制約がある現状は、余剰人員を抱えずに生産性を高めるチャンスだと肯定的に捉えられています。 - 日本企業の得意領域は、オペレーショナルエクセレンス、すなわち「そう簡単にできないオペレーショナルに複雑でややこしいことを実現する能力」にあるとする分析が興味深かったです。
これは、体格や規模で劣る競合他社に対し、相撲取りの舞の海戦略が通用する領域であり、日本企業が得意とするドメインです。例えば、かゆいところに手が届く観光業のホスピタリティや、正確無比な鉄道の運行能力がこれにあたるとの説明は説得力がありました。 - 一方で、この強みがテクノロジーで通用しなくなっているという分析も指摘されています。
昔のテレビ製造のような高度なすり合わせ力が活きた時代から、デジタル化された今はルールベース・アルゴリズムベースで動く仕事が急増し、その多くが生成AIに置き換わります。
これは、ゲームが野球からサッカーに変わっているのに、プレイヤーが野球しかできない状況であり、日本企業のコアコンピタンスが活きない危機を示しているとの指摘です。 - 社会機能の持続性については、スマートシュリンクの主張が現実的だと感じました。
人口減少社会において、僻地の道路修繕をあきらめ、農地を放棄するという主張は一見極端ですが、「コンパクト&ネットワークで多極集中」を目指し、収益力の低い団体が淘汰されていくことも已む得ない、という視点も説得力があります。 - エッセンシャルワーカーが様々なテクノロジーを駆使し、できるだけ少ない時間でできるだけ多くの価値提供を行い、できるだけたくさんの対価がもらえるようにして担い手も増やし、実質的な供給力を増やす。これは人手不足解消で社会機能の持続性を回復することであり、同時に働く人々の7割が従事するローカル経済圏の付加価値労働生産性と賃金と消費力を押し上げる。持続的な経済成長再生への(おそらくただ一つの)道であるとの指摘は、実現の難易度は感じるものの説得力がある主張です。
実務への示唆
- まず、生成AIに置き換わらない人間の仕事は、「問いを立てる部分」と「ディシジョン(決定)の部分」に残ると言われます。AIは問いを立てられず、意思決定には人間の直感や価値判断が不可欠だからです。そして、ある仕事がAIに置き換わっても、その仕事を通過体験的に行っておくことが必要だという指摘も重要です。経験がなければ、AIによる判断の根拠が不明瞭なまま、依存してしまうことになり、真のリーダーシップは発揮できません。
つまり完全にAIに任せるのではなく、AIで代替する業務をブラックボックス化せず、将来のリーダー候補に生きた経験をさせるために、あえて経験させる必要があるということです。実務者の立場からは、とても納得感のある指摘です。 - 考えさせられたのは、大企業のホワイトカラーは「なぜ自分の仕事に対価を払ってもらえるのか?」という付加価値を測る物差しが曖昧だという指摘です。
ぼんやりと広範囲の仕事をしていると、漫然と時間が過ぎ、人に語れる自分の強みがないまま埋没してしまうリスクを突きつけています。多くの方が真摯に向き合わないといけない問いでしょう。 - ローカル経由でグローバルリーダーを目指すアプローチとして、「ボス力」を鍛えるという指摘も非常に共感した点です。ボス力とは「自ら問題を提示し、答えを模索し、決断し、組織を動かして実行し、その結果を背負うこと」です。
これは、グローバルリーダーを目指す方のみならず、会社内で自身の価値を引き上げるうえで、大変有効なアプローチだと感じました。
個人的には組織を「結果を背負う覚悟」ありきでは、と考えるところです。
まず問題提起がなければ始まりませんが、覚悟がなければ、人を動かすことも躊躇われるでしょうし、実行も中途半端に終わってしまうものです。 - また、すべての知識労働の土台として、リベラルアーツの基礎が日本語の「読む力」と「書く力」にあるという主張も、常日頃感じているところです。「書く力」はセンスではなく、論理を構築しながら分かりやすく表現するトレーニングで体得できる力であり、自己投資すべき基礎中の基礎という著者の指摘はその通りで、鍛えれば論理的かつ分かりやすく書けるようになります。
総評
本書は、少子高齢化で、すさまじい速度でAIにホワイトカラーの仕事が代替されていく(すでに現在進行中)の日本において、今、その職(ホワイトカラー)の仕事にある方々がどう生き残るべきか、具体的な指針を与えてくれます。
全体を通じて、ホワイトカラーの働き方をどう変えるべきか?という大きなテーマについて、俯瞰的な視点で語られています。微細な論点に拘らず、その視点が一貫しているので、とても読みやすかったです。
本書は、「ホワイトカラー消滅」という刺激的なタイトルとは裏腹に、悲観論ではなく、ホワイトカラーの皆さん一人ひとりのキャリアと、日本の活路を示すための明確な具体的な行動指針が記載された一冊です。