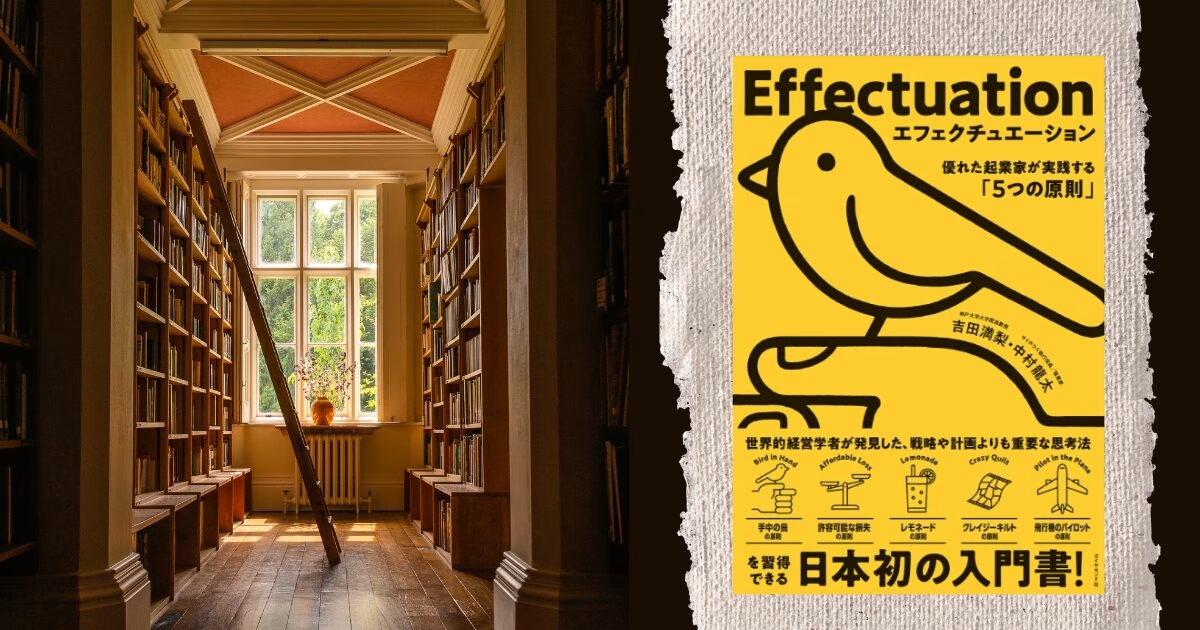概要
- タイトル:エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」
- 著者等:吉田 満梨、中村 龍太
- 出版社:ダイヤモンド社
本書の構成は次の通りです。
目次
はじめに
第1章 エフェクチュエーションとは何か
第2章 手中の鳥の原則
第3章 許容可能な損失の原則
第4章 レモネードの原則
第5章 クレイジーキルトの原則
第6章 パートナー獲得のための行動:問いかけ(asking)
第7章 飛行機のパイロットの原則
第8章 エフェクチュエーションの全体プロセス
第9章 フリーランスとしてのエフェクチュエーション
第10章 企業でのエフェクチュエーションマネジメント
おわりに
引用文献リスト
印象に残った論点
本書の核となる概念である「エフェクチュエーション(実行理論)」は、従来の「コーゼーション(予測理論)」と対比されています。
コーゼーションが「将来を予測し、目標達成のための最適な手段を講じる」というアプローチであるのに対し、エフェクチュエーションは「予測ではなく、手持ちの手段(リソース)を活用してコントロールし、未来を創造していく」という、極めて実践的な思考法です。
特に印象的だったのは、この理論が、既存顧客のニーズが不明瞭な新規事業や、最適なアプローチを定義できない困難な課題解決といった、「高い不確実性」を伴う取り組みにこそ適用できる点です。
この思考様式は、本書で紹介されている以下の「エフェクチュエーションの5つの原則」に集約されています。
- 手中の鳥の原則
「何がしたいか」ではなく、「手持ちの手段(能力、知識、人脈)から何ができるか」を考える。
任天堂のゲームウオッチ開発が、電卓チップという「手持ちの手段」から生まれたエピソードが象徴的でした。また、「Know Who(誰を知っているか)」においては、新しい情報をもたらす「つながりの弱い人たち」の重要性を指摘している点も、現代のネットワーク社会において示唆に富んでいます。
同質性の高い仲間とばかりの付き合いは楽ですが、エフェクチュエーションを実践するうえではコンフォートゾーンから抜け出すことが必要だなと、強く感じました。 - 許容可能な損失の原則
期待できるリターンではなく、「最悪うまくいかなくても許容できる損失」を基準に意思決定を行う。
これにより、挑戦への心理的ハードルが下がり、失敗を致命傷にせず再チャレンジを可能にします。失敗を学習機会と捉え直す視点は、革新を生むマインドセットの根幹です。 - レモネードの原則
予期せぬ事態や偶然を避けるのではなく、それをテコとして活用し、新しい価値を創造する。
3Mのポストイットが、「剥がれない接着剤」という目標からの失敗作を、フセンという革新的な製品に変えた事例は、リフレーミング(見方を変える)の典型例かと思います。 - クレージーキルトの原則
完成形を決めるのではなく、すべての関与者と交渉し、「パッチワーク」のようにパートナーシップを磨いていくことです。
ソニーではじめクレーマーのように思われていた音大の学生(大賀さん)が、ソニーの商品開発に積極的に関わるようになり、結果としてソニーに入社し、当時の組織にはなかった音楽のソニーという新たなビジョンを持ち込み、最終的に社長になった事例が典型例として紹介されています。この事例が示すように、「クレーマー」すら新たなビジョンを生み出すパートナーになり得ることが説かれています。
また、パートナーシップを得るためには、どんな形であれば協力を得られるか?を相手に問いかけることが重要という指摘も興味深かったです。売り込みはYES/NOの2択になるので、パートナーシップを得るうえでは不適なんですね。 - 飛行機のパイロットの原則
コントロール可能な活動に集中し、予測ではなくコントロールによって望ましい成果を帰結させる。
予測困難な環境下であったり、目的が不明瞭であったり、複数の選択肢の中で首尾一貫した選択が難しいケース、情報が多様でどこに注目すればよいか分からないケースは、発生した不確実性に都度対処するエフェクチュエーションがマッチする。
また、ヘンリー・フォードやスティーブ・ジョブズの言葉が示すように、革新的製品は「顧客ニーズ」から生まれたのではなく、自分の個人的な満足や不満足、経験に基づく知識や耳にした情報にイノベーションの機会が存在しているというこを示唆しているとの指摘も、非常に印象深かったです。
- ヘンリー・フォード
「もし人々に何が欲しいか尋ねたら、彼らはより速い馬と答えただろう」 - スティーブ・ジョブズ
「多くの場合、人々はそれを見せるまで、自分が何を望んでいるのか分からない」
実務への示唆
本書の教えは、起業家だけでなく、不確実性の高いプロジェクトに取り組む全てのビジネスパーソンにとって非常に参考になるものです。
- 新規事業開発やプロジェクトの立ち上げ時
- 分厚い市場調査や緻密な事業計画(コーゼーション)に過剰に時間をかけるのではなく、まずは「今、手持ちの資源(技術、スキル、人脈)で何ができるか?」からスモールスタートを切る(手中の鳥の原則)。
- そのアイデアを実行する際、初期投資の回収予測に注力するより、「最悪、この試みで失っても痛くない金額・時間」を設定し、その範囲内で迅速に行動に移す(許容可能な損失の原則)。失敗が許容範囲内であれば、その失敗は学習と次の成功への糧となります。
- 予期せぬトラブルへの対処:
- 計画から逸脱した事態(顧客からの想定外の要望、開発途中の予期せぬ成果など)が発生した際、それを「計画の失敗」とネガティブに捉えるのではなく、「このレモンでどんなレモネードが作れるか?」という視点で見方を変える(レモネードの原則)。
- チームビルディングと協業:
- 外部の協力者に「製品を買ってほしい/協力してほしい」と売り込む(Selling)だけでなく、「どんな形であれば我々の活動に協力できるか?」と問いかける(Asking)姿勢を持つ。この対話を通じて、予期せぬ協力の形や新しいビジネスモデルが生まれる可能性が高まります(クレージーキルトの原則)。
総評
私たちを取り巻く世界がますます複雑化し、予測の精度が低下していく今、「緻密な計画」の呪縛から解放され、エフェクチュエーションは「行動」と「柔軟な適応」によって未来を切り拓く力を教えてくれます。
本書には、不確実な時代に立ちすくむのではなく、進むための具体的な理論が詰まっています。
不確実性にぶつかっていくすべての実務家に強くお勧めしたい一冊です。
この実行理論を身につけることは、混迷の時代を生き抜くための「羅針盤」になるのはないでしょうか。