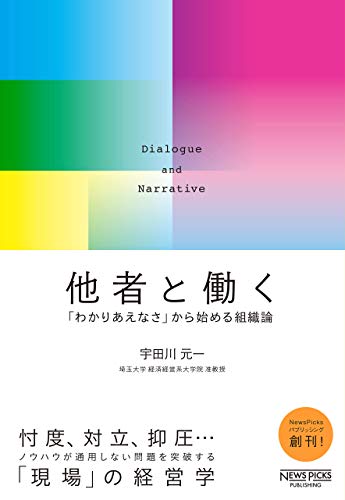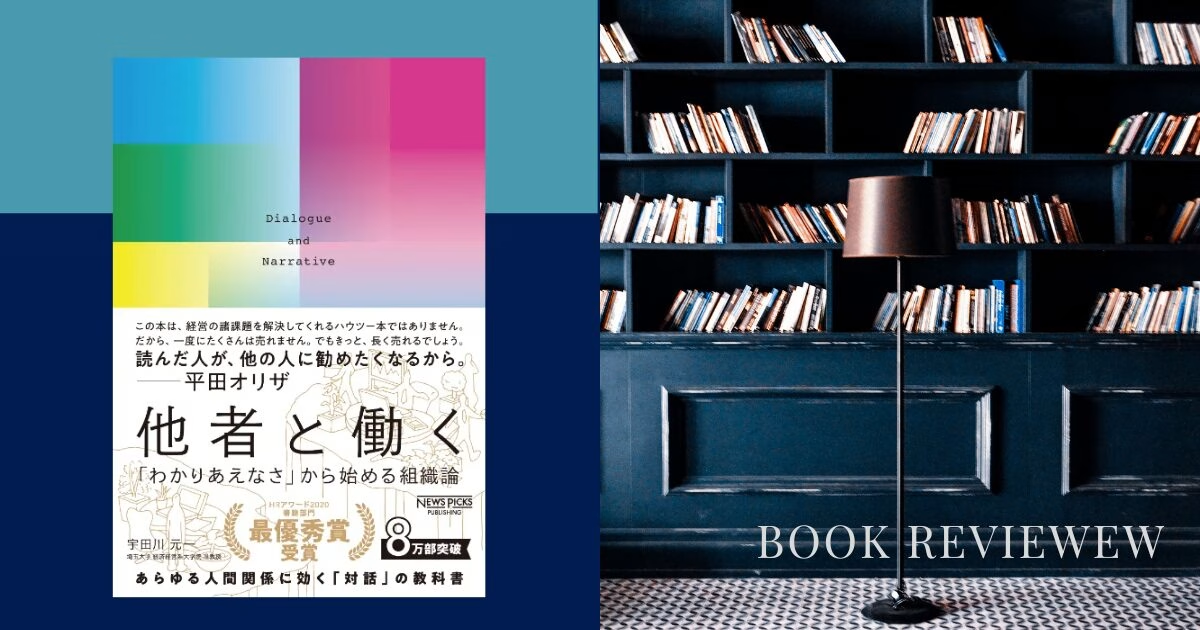概要
- タイトル:他者と働く 「わかりあえなさ」から始める組織論
- 著者等:宇田川 元一
- 出版社:NewsPicksパブリッシング
目次
はじめに
正しい知識はなぜ実践できないのか
第1章 組織の厄介な問題は「合理的」に起きている
第2章 ナラティヴの溝を渡るための4つのプロセス
第3章 実践1.総論賛成・各論反対の溝に挑む
第4章 実践2.正論の届かない溝に挑む
第5章 実践3.権力が生み出す溝に挑む
第6章 対話を阻む5つの罠
第7章 ナラティヴの限界の先にあるもの
おわりに 父について、あるいは私たちについて
印象に残った論点
本書では、問題を「技術的問題」と「適応課題」の二つに分類しています。
- 技術的問題
既存の知識や方法論で解決できる問題(例:喉が渇いたから水を飲む)。 - 適応課題
既存の方法だけでは解決できない、複雑で困難な問題。「見えない問題」「向き合うのが難しい問題」であり、解決には関係性の変革が不可欠。
私たちの職場で遭遇する問題の多くは、実は後者の「適応課題」であるという指摘は非常に印象的です。そして、その解決のために「対話」とは「新しい関係性を構築すること」だと定義している点も同様に印象的でした。
また、人間関係を「私とあなた(固有の関係)」と「私とそれ(道具的な関係)」に分類したマルティン・ブーバーの視点は、私たちが無意識のうちに人間を「道具」として見がちなビジネスの現場に警鐘を鳴らします。
家族・友人・部下といった身近な関係において、いかに「私とあなた」の関係性をベースにコミュニケーションを取るべきか、本書を読みながら私自身も深く考えさせられました。
さらに、“ナラティブ”(解釈の枠組み)という概念が、適応課題の核心にある「溝」の正体であり、対話とはこのナラティブの「溝に橋を架ける」行為であるという主張も、他者と働く組織における複雑なコミュニケーションを理解するための大きなヒントになるでしょう。
実務への示唆
本書は、特に適応課題への対処と組織内コミュニケーションにおいて、対話のプロセスと関係性変革のための指針を示しています。
「溝に橋を架ける」4つのプロセス
ナラティブの溝を埋めるための対話プロセスは、実務における難しい交渉や部門間対立を解決する実践的な手法です。本書では次の4つのステップが示されています。
- 準備(溝に気づく)
まず、相手と自分のナラティブに溝(適応課題)があることを認める。 - 観察(溝の向こうを眺める)
法務は法的リスク、営業は短期売上というように、相手のナラティブを解釈する軸を探る。 - 解釈(溝を渡り橋を設計する)
相手のナラティブを尊重しつつ、共通の目的を見つけるなど、新しい関係性の設計図を描く。 - 介入(溝に橋を架ける)
実際の行動を通じて、新しい関係性(橋)を築く。
関係性構築の変革
越境学習が注目される理由も、個人を変えるのではなく、個人が埋め込まれている「環境(関係性)」を変えることで、結果として個人が変わるという文脈で理解できます。
組織運営においては、「お互いにナラティブを主張して相手を変えようとする」ことは溝を深めます。そうではなく、「相手のナラティブをよく観察したうえで、相手がより良い実践ができるように支援する」という姿勢が、最終的に自分も他者も両方が生きられる関係の構築に繋がります。
例えば、上司への提案が受け入れられないとき、相手を悪者にするのではなく、「上司は異なるナラティブの中にいて、見ている点が違う」と自分のナラティブを脇に置いて観察できるかということです。これはまた、立場の弱い側が陥りがちな「上司を悪者にして自分を正当化する」という罠から脱するための鍵にもなります。
総評
本書は、現代社会やビジネスにおける複雑な問題(適応課題)を解決するための「対話」の重要性を深く掘り下げた一冊です。
単なるテクニック論に終わらず、マルティン・ブーバーの哲学やハイフェッツのリーダーシップ論といった理論的な裏付けを持ちながら、ナラティブの概念や「溝に橋を架ける」プロセスなど、実践的なフレームワークを提供してくれます。特に、立場が異なる人とのコミュニケーションに悩んでいる方、会社のみならず家族や友人との関係性をより良くしたいと考えている方にとって、自己の「偏り」を認め、対話を実践することの大事さに気づかせてくれるでしょう。
上司への提案が通らない、チームが機能しない、部門間で協力が進まないといった課題を抱えている方に、「問題の核心はどこにあるのか」「どうすればその溝を越えられるのか」という本質的な問いと、その解決への道筋を与えてくれる対話の教科書のような一冊です。