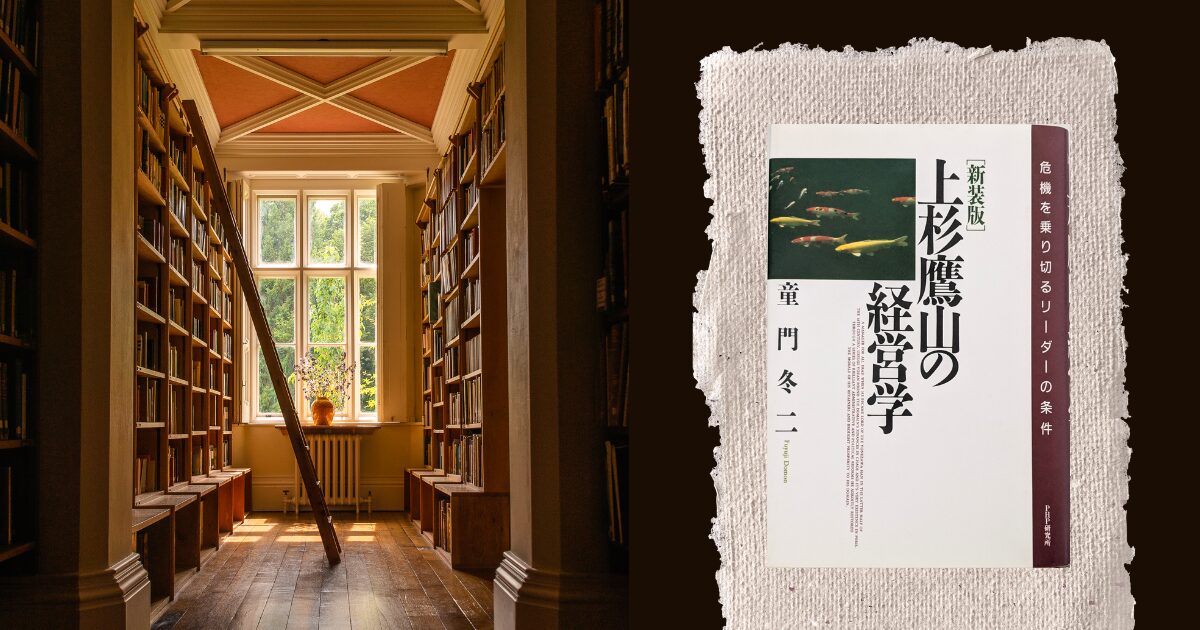本の概要
タイトル:上杉鷹山の経営学 危機を乗り切るリーダーの条件
著者等:童門 冬二
出版社:PHP文庫
あらすじ
「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」
誰もが一度は耳にしたことがある、この力強い言葉を残した江戸時代の名君、上杉鷹山(うえすぎようざん)。
彼が藩主を務めた米沢藩は、実は当時、財政破綻寸前の危機的状況にありました。
本書『上杉鷹山の経営学』では、鷹山がいかにしてこの難局を乗り切り、豊かな藩へと導いたのかを、現代のビジネス社会にも通じる「経営」という視点から紐解いていきます。
著者は、これらの改革を成功に導いた鷹山のリーダーシップから、
- ビジョンの明確化
- 現場主義
- 人材育成
- 情報共有
- 常に学ぶ姿勢
といった、現代のビジネスリーダーにも通じる重要な要素を抽出しています。
ジョン・F・ケネディ大統領が生前に「あなたが最も尊敬する日本人は誰ですか」と聞かれ、その答えに上杉鷹山の名前を挙げたのも、読んで納得する一冊です。
学びと共感
経営改革実行の要諦
本書の中で著者は、上杉鷹山の経営改革実行の要諦が、次の各ポイントにあると分析しています。
〇改革を妨げる壁が、三つあることを示したこと
① 制度の壁
② 物理的な壁
③ 意識(心)の壁
〇改革とは、この三つの壁を壊すことであると告げたこと。
中でも、特に壊さねばならないのは、③の“心の壁”であることを強調したこと。
〇そのために、 次のことを実行したこと。
① 情報はすべて共有する
② 職場での討論を活発にする
③ その合意を尊重する
④ 現場を重視する
⑤ 城中(藩庁)に愛と信頼の念を回復する
鷹山は「徳」を政治の基本におき、それを経済に結び付けました。
彼は倹約一辺倒論者ではなく、「生きた金」は惜しみなく使っている点にも注目です。
トップに立つ者の姿勢 限界を認める勇気と人材活用
鷹山は、家臣に自己の限界を明示しました。これは自らの強いリーダーシップで藩政を行う藩主が当たり前だった当時では、極めて珍しい藩主の姿勢であったでしょう。
ただ、鷹山は自己の限界を明示するだけでなく、一人では限界があるからこそ家臣に協力を求めたのでした。つまり、絶対的な君主のように全てを自己に集中させるのではなく、また上からの押し付けでもなく、家臣に藩政への参加を求めたのです。
有能な人材を活かすことは、まさに経営における普遍の原則です。
当時からそれを体現していた鷹山はやはりすごいと感じます。
情報の偏重を避けるための「情報の共有」は既にご紹介しましたが、他にも「コミュニケーション回路を太く短く設定する」「トップダウンとボトムアップを滑らかにする」などの工夫があったと著者は分析していて、今の経営においても参考になる示唆に富んでいます。また経営者のみならず、部下を持つ管理職にも大いに参考になります。
そういえば「恐れのない組織」でも「知らないと認めると、信用を失うどころか、逆に信用を得ることになる」とありました。鷹山と似ているかもしれませんね。
トップに立つ者の姿勢 現場を重視し、正しい情報を把握する
本書では「鷹山は人間一人ひとりを見つめることによって、藩の実態を知っていった。つまり人間に現れている現象がそのまま藩の実態を表していると見たのである。人を知れば知るほどその分だけ米沢藩の実態を知った。一人ひとりに現れている実態の総和によって鷹山は次第に頭のなかに米沢藩の実像を構築していった。」とあります。
これは現場を重視するという経営者の姿勢と重なります。
経営においては、正しい理解のうえに正しい判断がなされる必要があります。しかし、いくら優秀な経営者でも間違った事実認識に基づいてしまうと、当然ながらその経営判断は的はずれになってしまいます。経営者でなくとも、日常的に判断する立場にある管理職の方も同様です。
判断のスピードを求められる状況においては、限定的な情報で判断せざるをえないケースもあるかもしれません。ですが、そういった場面においても日頃から正しく現状を理解できていれば正しく判断できる確率は高まるでしょう。
鷹山は、農地を見て回る際にも「普段の様子を見たい、皆に負担を掛けたくない」として、特別な用意を嫌ったと言われています。当時、お殿様が自分たちの田んぼにくる場合、道路を履き、精一杯のご馳走を用意するなど事前にしっかりと準備をして、実際にお殿様が来た時には農作業は中断して出迎えるということが当たり前でした。
そういった時代背景の中で、何ら準備不要で農作業の手を休める必要もないとした鷹山のスタイルっは、当時としては異例中の異例であったようです。
トヨタやホンダなどの自動車メーカーが“現場”“現物”“現実”の3現主義を実践していることは有名ですが、鷹山は江戸時代からこれを実践していたことが伺えます。
トップに近づけば近づくほど、一次情報が届きにくくなります。
「自分の目で確かめ」「自分の耳で聴き」「自分の肌で感じ」「自分で考える」ことの重要性を再確認させられます。
トップに立つ者の姿勢 歴史(失敗)から学ぶ
鷹山は、享保の改革や松平定信による幕府の行政改革がうまくいかなかった理由を自分なりに分析し、そこから学ぶ姿勢が突出しています。
この「歴史(失敗)から学ぶ」という姿勢が、鷹山の特徴として挙げられるように思います。
こういった鷹山の姿勢と藩の現状に対する正しいが紐付いて「改革の根本に優しさといたわり、思いやりが欠けている」「自分の経営改革は決して藩財政を富ませるために行うのではなく、むしろ藩民を富ませるために行うものでなければならない」いう着眼につながったのではないでしょうか。
トップに立つ者の姿勢 誤って改むるに憚ることなかれ
鷹山の信条は「誤って改むるに憚ることなかれ」です。
孔子の言葉で論語に出てくる一節ですが、言うは易し行うは難しの典型で、これを実践することって難しいですよね。過ちだと認めたくない自分との葛藤もあるでしょうし、下手をすれば朝令暮改と紙一重で、周囲の批判にさらされるリスクもあります。
指示や判断の間違いに気づいても、多くの人がすぐに訂正できず、二の足を踏んでしまうのが現実ではないでしょうか。
ですが、これを実践できているところが、鷹山のすごみだと感じました。
絶対に間違わない人などいないので、その意味でもとても重要な信条だと思います。
激動の時代を生き抜いた名君の「不屈の精神」と「民を想う心」から、現代社会におけるリーダーシップの真髄を学び、自身の仕事や人生に役立ててみてはいかがでしょうか。
歴史書としても、ビジネス書としても楽しめる一冊。
おすすめです!