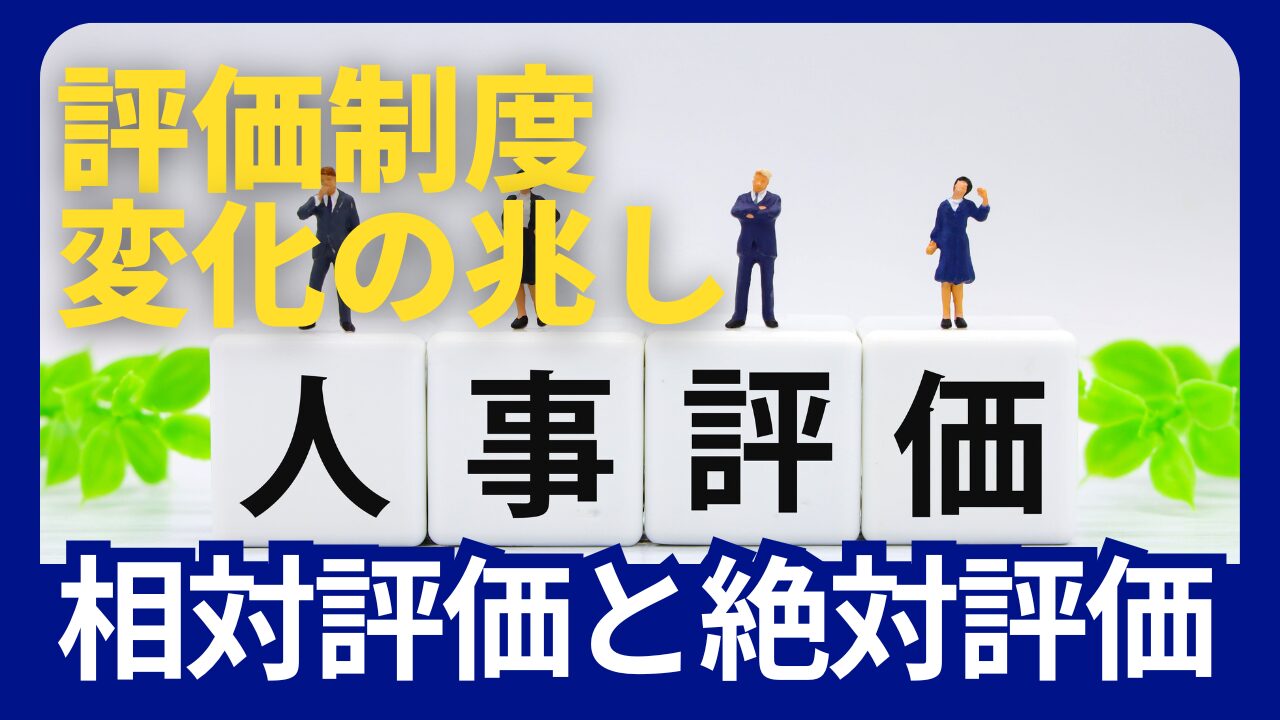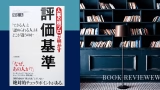日本企業の評価制度は相対評価が主流ですが、近年、この人事考課に対する考え方に変化の兆しが見られます。
今回は、相対評価と絶対評価のメリット・デメリットを比較しながら、日本企業が今後どちらを選択していくべきかについて考えていきます。

1.相対評価とは?
相対評価とは、社員を同じ部署や職級内で比較し、その中での相対的な位置づけに基づいて評価する制度です。
部署内で営業成績1位の人がS評価、次にA評価…といったように、順位付けで評価が決まります。相対評価では、各評価ランクの人数比率(出現率)があらかじめ決められていることが多く、例えば、S:A:B:C =10%:20%:40%:30%のように設定されます。
被考課者の数に対してSやAなどの評語の出現率が決まっているため、いくら自分の成績が良くても、さらに上位成績の社員がいると、自分の評価が上がらない可能性があります。
例えるなら、運動会の100メートル走です。いくら自分の足が速くても、自分以上に足が速い友人と一緒に走ると、自分は1位になれません。相対評価は、運動会の100メートル走に似ているといえるでしょう。
2.絶対評価とは?
絶対評価は、あらかじめ設定された基準に対して、どれだけ達成できたかで評価する方法です。他の社員との比較ではなく、個人の目標達成度や能力の発揮度合いに基づいて評価が行われますので、自分成績次第で高評価が期待できます。
絶対評価では、売上目標10億円を達成すればS評価、売上目標7億円を達成すればA評価というように、設定された基準を設定します。その基準を達成すれば、事前に決められた評価を得ることができます。
他者の成績に関係なく、目標を達成すれば高評価を得られるため、全員が高評価になる可能性もあります。
例えるなら、大学の成績評価です。テストで、90点以上が秀、80点以上が優という、あらかじめ定められた基準をクリアすると、それに応じた評価がつけられます。絶対評価は学校の成績評価に似ているといえるでしょう。
3.相対評価と絶対評価の比較表
相対評価と絶対評価の特徴やメリット・デメリットなどを一覧表としてまとめました。
| 項目 | 相対評価 | 絶対評価 |
| 評価基準 | 同じ部署や同じ業務担当、または、同じ職位や職能等級内の他の社員との比較 | 目標達成度や能力発揮度合いなどの評価基準について、事前設定した基準を達成したかどうかを個人単位で評価 |
| 評価分布 | 予め決められた比率に基づき、評価が分散する | 評価の分布は基準達成度によって変動し、固定されていない |
| メリット | ①社員間の競争を促し、組織全体のパフォーマンス向上に寄与する ②予算管理が容易 | ①評価基準が明確で分かりやすく、個人の成長を促しやすい ②個人の頑張りが直接評価に反映されるため、モチベーション向上に繋がりやすい |
| デメリット | ①社員間の協力関係が薄れる可能性がある ②成績が上がっても評価が上がらない場合がある ③評価基準によっては評価者の主観が入りやすい | ①評価基準の設定が難しく、評価者や担当業務によって評価にばらつきが出る可能性がある ②評価が中間や上位に固まり、人件費の上昇につながる可能性がある ③目標達成に注力しすぎて、他の業務がおろそかになる可能性がある ④予算管理が難しい |
| 社員への影響 | 周囲との競争を意識した働き方になりやすい | 自分自身の目標達成に集中した働き方になりやすい |
| 適した組織 | ①社員間の競争を重視する組織 ②社員が多い大企業 ③予算管理に厳格な企業 | ①企業 個人の能力開発や自主性を重視する組織 ②社員数が少ないスタートアップ ③評価者の力量が高い企業 |
4.相対評価のメリット
相対評価のメリットについて、それぞれご説明いたします。
社員間の競争を促し、組織全体のパフォーマンス向上に寄与する
相対評価は、基準を上回るのではなく他者を上回ることで良い評価が得られる仕組みなので、いわば社内の同僚がライバルになります。そのため、自然と社員間の競争が促進されます。うまく運用すれば、社員間の切磋琢磨による組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。
予算管理が容易
多くの企業が、前年評価や半期評価を季節賞与に反映しています。その反映方法は、S評価なら1.5倍、A評価なら1.2倍など、評語ごとの係数を設定し、前年評価や半期評価の結果に応じて賞与金額に乗算するという方法が一般的です。
この場合、賞与引当手金を計上することで会計上の費用を当期分に対応させます。例えば、当期の夏季賞与の考課対象期間が前期10月から3月の下期の場合、前期の費用として夏季賞与の賞与引当金を計上することで、考課対象期間と費用発生時期を対応させるわけです。
賞与引当金をどこまで厳密に計算しているかにもよりますが、相対評価の場合、評語の出現割合の上限が決まっているので、賞与の金額をある程度正確に見積もることができます。
そのため、計上した引当金と実際の賞与支給額に乖離が生じにくくなります。
またそれは、引当金と実際の支給額だけでなく、予算立案時の人件費予算も同様です。
次年度予算の立案においても賞与支給額を計算する必要がありますが、評語の出現率上上限が決まっている相対評価の場合、賞与支給額の上限を計算することができるので、きっちりと予算を計上することができます。そのため、評価のブレを理由として賞与支給額が予算を超過することはありません。
なお、課やグループ単位では絶対評価で評価され、部門や事業部など大きな組織単位になって相対評価が適用されるという企業も多くあります。この場合、最終的に相対評価で評語の発生割合を調整しているので、企業全体としては相対評価になります。
5.相対評価のデメリット
相対評価のデメリットについて、それぞれご説明いたします。
社員間の協力関係が薄れる可能性がある
相対評価は、組織のパフォーマンス向上を企図するというよりも、相互の競争意識を高めることで、個人のパフォーマンス向上を狙った評価方法 になります。
社員間の競争が促進されるということは、その裏返しとして社員間の協力関係が薄れる可能性があります。
成績が上がっても評価が上がらない場合がある
運動会の100メートル走に例えたように、いくら自分の成績が良くても、それ以上に良い成績の同僚がいると、自分は一番をとれません。
例えば、自分の売上予算の達成率が110%だった場合を考えてみます。売上予算達成率が110%なら良い評価を得られそうですが、もし他の社員の売上予算の達成率が120%を超えていると、いくら自分の売上予算の達成率が110%だとしても、他の社員の方が良い評価を得ることになります。
評価が相対的なので、周囲の評価に影響を受けてしまうことは避けられません。
評価結果に対する納得性が高まりにくいといわれる所以です。
ただし、これは必ずしもデメリットだけではありません。
もし、自分の売上予算達成率が90%で予算達成率は100%を割っていても、他の社員の売上予算達成率が80%以下だったら自分の評価は良いものとなるでしょう。
このように、もし市況が悪く、外勤営業職の予算達成率が軒並み悪くとも、相対評価の場合はある程度救済することができます。
評価基準によっては評価者の主観が入りやすい
複数の要素で相対評価を行う場合、比較する要素が「成績」や「コミュニケーション能力」など多岐にわたり、評価者がどれを重視するかによって結果が変動する場合があります。
また、相対評価は絶対評価と比較して定量的で明確な評価基準を定めずとも運用できてしまうため、そもそもの評価基準が曖昧な場合があります。評価基準が曖昧だと、評価者は被考課者の日頃の印象や態度に影響される等、評価者の主観が入りやすくなります。
ただ、これらは、具体的な行動に焦点をあてて評価項目ごとのウエイトをきちんと設定した評価シートを作成したり、できるだけ定量的な目標を設定することで予防が可能です。
6.絶対評価のメリット
絶対評価のメリットについて、それぞれご説明いたします。
評価基準が明確で分かりやすく、個人の成長を促しやすい
絶対評価は、事前設定した基準を達成したかどうかで評語が決まります。そのため、絶対評価を運用するためには、明確な評価基準の設定が不可欠になります。
社員は明確化された目標の達成に取り組むため、個人の成長が促進されやすい評価方法になります。
個人の頑張りが直接評価に反映されるため、モチベーション向上に繋がりやすい
相対評価の場合、いくら自分の成績が良くても、必ずしも良い評価を得られるとは限りませんが、絶対評価の場合は自分の成績に応じた評価を得ることができます。
他の社員の成績は関係ありません。良くも悪くも自分次第であり、自分が頑張った結果としての成果は、そのまま評価に反映されます。そのため、相対評価と比較して絶対評価の方が社員のモチベーションが高まりやすいといえます。
7.絶対評価のデメリット
絶対評価のデメリットについて、それぞれご説明いたします。
評価基準の設定が難しく、評価者や担当業務によって評価にばらつきが出る可能性がある
これはメリットの裏返しになりますが、事前設定した基準を達成したかどうかで評語が決まるため、達成基準の設定に非常に神経を使います。
会社では、全員が同じ業務を担当しているわけではありません。職種や部門によって成果の測定しやすさに差があるのが通常です。そのため、部署ごとや社員ごとで適切な達成基準が設定できないと、ある社員にとっては難易度が高く、ある社員にとっては難易度が低くなってしまいます。そうなると評価結果はバラツキますし、評価の公平性を損ねることになります。
加えて、評価者は部下との良好な関係維持や衝突回避のため、甘い評価を与える傾向があります。評語の出現率の上限が決められていなければ、上位評語を多く出すことができるので、どうしても上振れしやすくなってしまうのです。
したがって、運用においては評価者の力量が重要です。一人ひとりに適した達成基準を設定するという力量であり、寛大化傾向などのバイアスに左右されず適切に評価を行うことができる力量です。評価者を育成するためのトレーニングも重要です。
評価が中間や上位に固まり、人件費の上昇につながる可能性がある。
期初に適切な達成基準が設定できても、取り巻く環境の変化によって、常に達成の難易度は変化します。仮に市況が良くて、半期終了時点で営業職全員の達成率が150%で、期末に向けてさらなる活況が予想されたとしても、期中に達成基準を厳しくすることは社員の理解を得られないでしょう。そうすると、評価が上位に固まってしまい、思わぬ人件費の上昇につながってしまう可能性があります。
また、その逆に評価が下位に集中してしまったら、いくら期初に話し合った達成基準だとしても社員が不満をためてしまう可能性があります。
目標達成に注力しすぎて、他の業務がおろそかになる可能性がある
絶対評価では、相対評価と比較して、より具体的・定量的に達成基準を定める必要があります。そして、その基準を達成すると、決められた評語を得ることができるので、わかりやすく明確である一方で、具体的・定量的に定める基準さえクリアすればよいと考える社員も発生してきます。
こういった社員が出てくると、評価の対象になっていないものがおろそかになってしまう可能性があります。
この対策としては、目標管理だけでなく、行動やプロセスも評価対象に加えることで予防が可能です。
予算管理が難しい(引当金を超えた賞与実績の発生可能性がある)
多くの企業が評価結果を賞与に反映していますが、絶対評価の場合、相対評価と異なり評価してみないと、どの評語がどのくらいの割合で出現するのか分かりません。
そのため評価結果によっては、予算立案段階に見込んでいた賞与金額を超過してしまう可能性があります。そうなると、本決算のタイミングで賞与引当金を追加計上したり、期中で予算外の賞与引当金を追加計上する必要が生じ、年度決算や月次決算に影響を与えます。
したがって、絶対評価は予算管理を重視する企業では採用ハードルが高い評価手法といえます。
8.相対評価と絶対評価 どちらが良い?
ここまで見てきたとおり、相対評価と絶対評価でどちらが優れているかという議論は、それほど意味がありません。重要なことは、自社の評価制度の目的・自社の組織風土に合わせて選択するということです。

社員間の競争を促進したいのか? 競争による組織全体のパフォーマンス向上を目指すのか?
それとも育成や社員間協調を目指すのか? 社員のモチベーション向上を重視するのか? という違いに着目して選択します。
他にも、自社が人件費に関する予算管理に厳格なのか、人件費の期中増減に寛大なのかも重要なポイントで、自社の考え方も考慮しながら検討していきます。
また、自社の評価者に、部署ごと業務ごとの達成基準、評価ランクごとの達成基準を適切に設定できるだけの力量があるのか?その力量がないなら、どのようにトレーニングしていくのか?という自社の評価者の能力・練度にも影響を受けます。
つまり、相対評価と絶対評価のどちらを選択すべきか?という問いに対する答えは、どちらが自社で運用可能かという現実的な視点のみならず、自社の評価制度の目的をどう設定するか?ひいては自社の組織風土をどのようにしていきたいか?というビジョンによって変わるということに他なりません。
日本の評価制度の主流は相対評価です。これは伝統的に評価制度が会社側の視点で設計されてきたことが多分に影響していると思います。
予算管理はその代表例で、相対評価の方が会社にとって都合が良いため、相対評価が主流になっているわけです。
しかし、昨今は人的資本経営が注目され、企業の人材に対する考え方が転換してきており、それが評価制度の選択にも影響を与えてきていると感じます。
今は、いかに社員のモチベーションを高めるか、いかにパフォーマンスや納得性を高めるかという社員起点で評価制度が語られる場面が増えています。
また、社員一人ひとりの評価の納得性よりも、相対評価による部門ごとの評価の偏りの抑止といった全体最適が重視されてきました。
今、この優先順位が変わりつつあります。
それはつまり、社員一人ひとりの評価を最適化するという試みであり、人事評価においては全体最適から個別最適に移行してきていると捉えることもできるかもしれません。
9.絶対評価を採用している企業例
最後に絶対評価を導入している企業を1社ご紹介します。
◎リコーリース
リコーリースでは2020年10月から人事制度に絶対評価を導入しています。同社の絶対評価では、上司部下の対話に基づいて達成度を設定することはもちろん、業務の難易度基準票の作成による評価基準の調整、評価者研修の実施など、絶対評価を適切に運用するための工夫がみられます。
この絶対評価制による評価制度は、同社のHPで説明されています。
よろしければチェックしてみてください。
10.まとめ
相対評価でも絶対評価でも、社員一人ひとりを適切に評価するための方法論であるという本質は変わりありません。
最近は、ワンオンワンなど上司部下のコミュニケーションを踏まえて処遇を決めるなど、ノーレーティングによる評価方法が話題です。そして、ノーレーティング=絶対評価という文脈で語られることが多いと思いますが、必ずしもノーレーティングが絶対評価とは限りません。ノーレーティングでも人件費予算枠を超過しないようにコントロールしていたなら、それは絶対評価というよりも相対評価よりの運用です。
ノーレイティングは絶対評価や相対評価とは異なるもので、目標管理制度や360度評価などの評価手法の一つだと捉えた方がニュアンスとしては分かりやすいように思います。

さて、ここまで特徴やメリット・デメリットを比較しながら相対評価と絶対評価を概観してきました。
近年は絶対評価を導入する企業も増えてきていますが、ご紹介したリコーリースのような絶対評価を導入している企業は、まだ多くありません。
評価制度とは、社員の能力・行動・成果や組織への貢献度を、昇給・昇格や賞与に反映させる重要な仕組みです。
その重要な仕組みを「他社が導入している」ことを理由に、自社の評価制度を相対評価から絶対評価に切り替えても上手くいかないことは明白です。
繰り返しになりますが、評価制度は自社が考える評価の目的や目指す組織風土に合わせて選択していくことが重要です。
人的資本経営が標榜され、VUCAの時代にすごい勢いで社会も自社も変化している現代において、人事評価制度がずっと変わっておらず制度疲労を起こしているということがないよう、適宜点検してみられるのも良いかもしれません。
評価制度の見直しには非常に大きなパワーが必要です。
とても大変な仕事ですが、一方では大変やりがいのある分野だろうとも思います。人事に携わる方の頑張りどころではないでしょうか。
社員と会社を成長させる評価制度の模索は、まだまだ続きそうです。