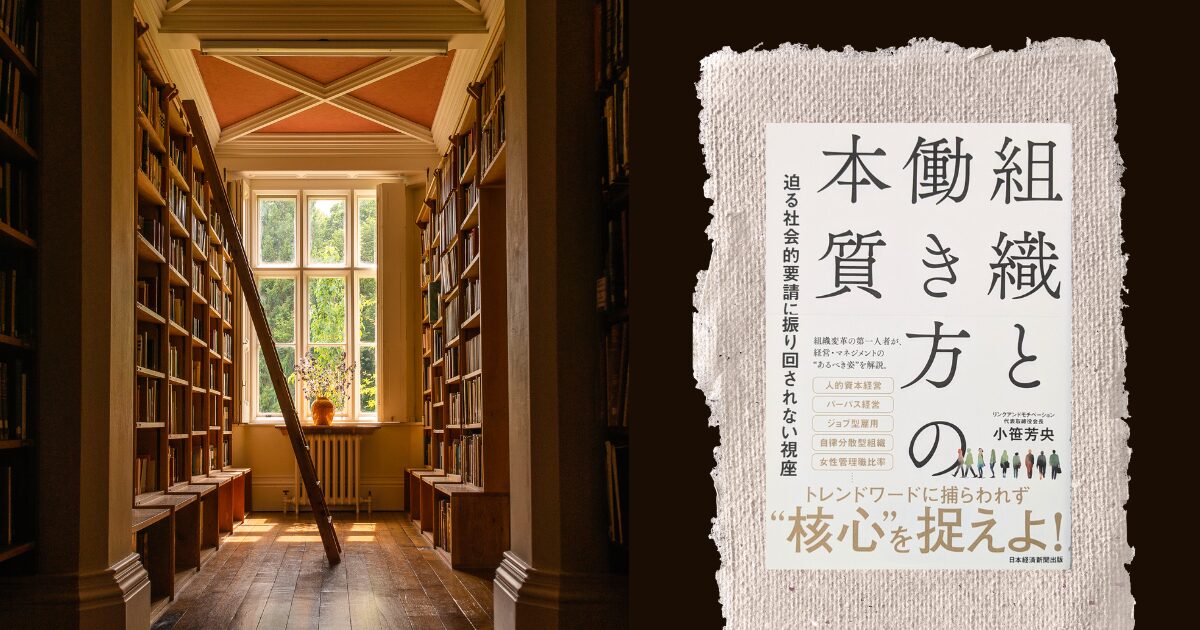本の概要
タイトル:組織と働き方の本質
著者等:小笹芳央
出版社:日本経済新聞出版
あらすじ
『組織と働き方の本質』は、リンク&モチベーション株式会社の創業者である小笹芳央氏が、長年の組織人事分野での経験をもとに、昨今の社会的要請やバズワードの本質を掘り下げる一冊です。
1.会社・組織・マネジメントの本質
経営者や管理職が持つべき本質的視座を示し、組織運営の土台を明確化します。企業や組織の存在意義やマネジメントの基本的な役割を問います。
2.社会的要請の本質
働き方改革や多様性推進など、近年の社会的要請の背景を分析し、その表層的な動きに振り回されることなく本質を捉える重要性を説いています。
3.個人の働き方の本質
個人の意欲(WILL)、能力(CAN)、そして組織として求められる役割(MUST)のバランスを意識した働き方について解説。個人と組織の関係性や個人のモチベーションを高める仕組みづくりを提案します。
4.組織変革の本質
組織の変革を成功させるための根幹となる考え方を示し、具体的なケーススタディや実例を通じて変化を促す方法論を紹介します。
5.環境変化適応の本質
経済や技術の急速な変化に対応するための組織の柔軟性や適応力の重要性を説き、持続可能な成長に寄与する組織のあり方を提言しています。
本書は経営者や管理職だけでなく、すべてのビジネスパーソンにとって、組織と働き方の根本的な意味を探り、実践に活かすための示唆が詰まっています。
文字も大きく行間も広くて、サクサク読めます。
著者の考えはもちろん、昨今の社会的要請やバズワードを把握するうえでも役立つ一冊です。
学びと共感
1.組織変革は小さなアクションからはじまる
変化対応力、適応能力、レジリエンスなど言葉の違いはあれ、誰しもこういった能力を備えた人材を採用したいし、育成したいと考えます。
変革を主導する人材が多数おられる組織は素晴らしい組織ですが、多くの企業では変革を主導する人材が乏しいという悩みをお持ちかと思います。経営者や管理職のみなさんに共通する悩みではないでしょうか。
本書では、日常的な挨拶という卑近な例を出して、小さなアクションが組織変革のきっかけであると説明しています。
組織変革に対して、ほとんどの人が最初は「様子見」を決め込むけれども、小さなアクションを続ければ、フォロワーが増えると説きます。
これを私なりに解釈すると、大きな変革を生み出せる人材でなくとも、誰もが組織の変革者になれるという意味だと捉えました。
小さなアクションでも継続すれば、誰もが変革を生み出す人材になれるというメッセージだと受け止めています。
この小さなアクションを起こすこと、またそれを続けることも難しいことですが、いきなり大きな変革を起こすことと比較すれば、いくらか難易度は低いでしょう。
2.キャリアデザインの幻想
著者は、キャリアはデザインする(できる)ものではないと主張されています。
私自身も常々そう考えていたので、この主張にはとても共感いたしました。
キャリアに関しては、「ブランド・ハップンスタンス理論」という有名な理論があります。
本書でも紹介されていますし、私もキャリアコンサルタント試験を受検するときに勉強して、気に入っている理論です。
ブランド・ハップンスタンス理論とは、1999年にスタンフォード大学のクランボルツ教授によって提唱された「個人のキャリアの8割は偶発的な出来事から生じる」という理論です。
クランボルツ教授は、個人のキャリアの8割が、予想できない偶然の出来事によって左右されていると説きます。そして、この偶然の出来事を本人が主体的に活用することで、キャリアアップにつながり、また単に偶然の発生を待つだけでなく、意図的に生み出せるような積極的な行動が重要であるということが、この理論の中核です。
私も複数の職種や部門の異動を経験しました。
もちろん部門異動は自分が決めたり希望したことではありませんでしたが、結果として自分の幅を広げるうえでとても貴重な経験だったと捉えています。
さらには転職も経験しています。
転職は自らが望んだことですが、自分が転職を決意したタイミングで、自らが希望する業種や職種やポジションの募集があるかは、もう完全に偶然性に左右されます。
”縁”と表現されることも多いでしょう。
まさに、偶然の出来事を本人が主体的に活用することで、キャリアアップにつながり、また単に偶然の発生を待つだけでなく、意図的に生み出せるような積極的な行動と言えるのではないでしょうか。
きっと似たような経験は、きっと皆さんもお持ちだろうと思います。
ブランド・ハップンスタンス理論は、まだまだ現役の理論ですね。
3.組織とは要素還元できない協働システムである
要素還元できないとは、つまり関係論で考えるということです。
仮に5人の組織を要素還元すると「Aさん~Eさんの5名の従業員がいる」となりますが、関係論的な考え方だと「Aさん~Eさんには10本の関係(5×4÷2)がある」となります。
これが関係論的な考え方で、組織を考えるうえでは、この関係性を縮減するかが重要になってくるという著者の主張も、大いに理解・共感するポイントでした。
フラットな組織が流行していますが、この考え方は経営組織を考えるうえで、無視できない考え方だと思います。
4.現在の会社と個人の関係は、「縛り、縛られ合う」関係ではなく、「選び、選ばれ合う」関係である
おそらく皆さんも同じことを感じておられるのではないでしょうか。
私は人事という立場ですので、特に「選ばれる」という点を強く意識しています。
中堅企業や中小企業においては、この視点が欠落してしまうと、もう採用できなくなるのでは?離職率が跳ね上がってしまうのでは?という怖さすら感じます。
求職者や現在頑張っている従業員のみなさんから選ばれ続ける会社になるために何ができるのか?
これを問い続けていきたいと、改めて感じさせられました。