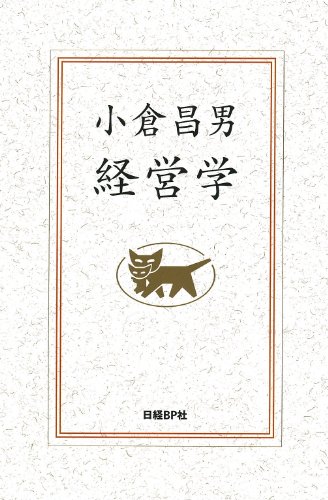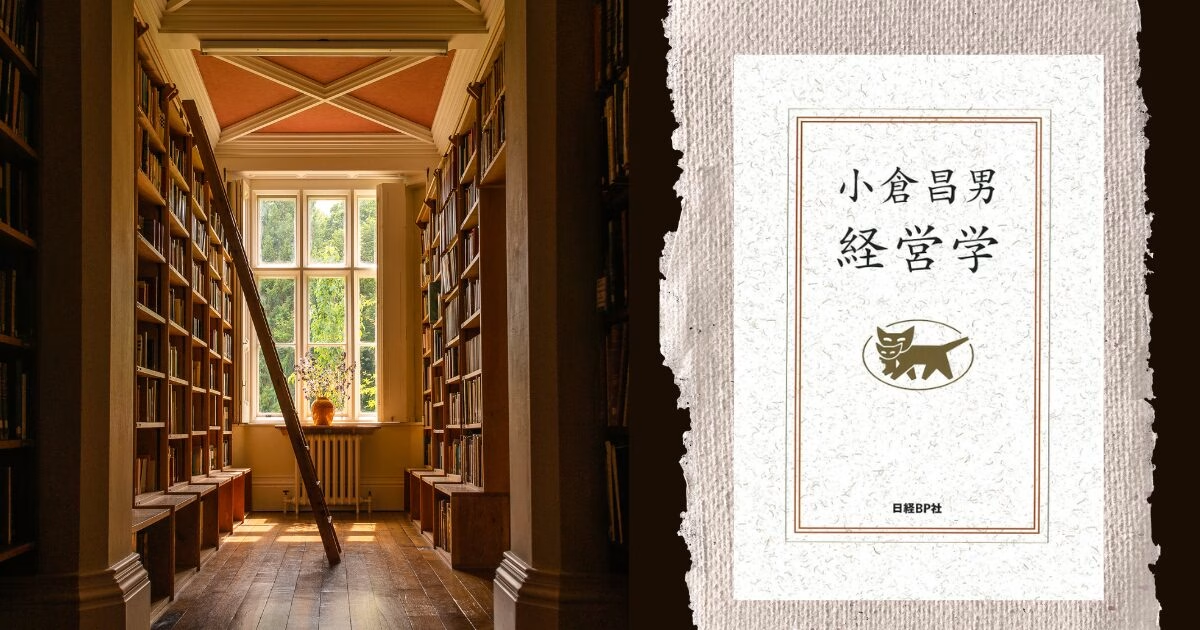本の概要
タイトル:小倉昌男 経営学
著者等:小倉昌男
出版社:日経BP
あらすじ
『小倉昌男 経営学』は、クロネコヤマトの宅急便を生み出し、日本の物流業界に革命を起こした伝説の経営者・小倉昌男氏の経営理念と実践知が詰まったビジネス書です。
「宅急便」って、もはや私たちの生活になくてはならないサービスですよね。 でも、どうやって生まれたか、考えたことありますか?
小倉昌男とは?経歴と功績を徹底解説
1924年生まれの小倉昌男氏は、父親が創業したヤマト運輸を引き継ぎ、当時の運輸業界の常識を根本から覆す改革を実行しました。同氏の最大の功績は1976年に始めた「宅急便」サービスです。法人向け大口輸送が主流だった時代に、個人客向けの小口配送市場を開拓するという革新的な挑戦でした。
成功するビジネスリーダーの思考法
小倉昌男氏の経営哲学の核心は「サービスが先、利益は後」という顧客中心主義です。この考え方が、後の宅急便の爆発的成功の原動力となりました。また「現場主義」を徹底し、経営者自らが現場の声に耳を傾け、顧客のニーズを直接把握することの重要性を説いています。
社会貢献とビジネスの両立方法
62歳で社長を退任した後の取り組みも特筆すべきです。小倉昌男氏は私財を投じて障害者雇用の「スワンベーカリー」を設立。単なる慈善事業ではなく、経済的に自立可能なビジネスモデルを構築した先駆的な社会起業家としても高く評価されています。
学びと共感
自身の経験を元に語る内容は、そのどれもが「なるほど」と感じさせるものです。
書中に「経営とは論理の積み重ねであり、考える力がなければ経営者とはいえない」と出てくるのですが、その論理をどのように導き、そして実践していったのかについて、経営者視点で書かれています。どれもが印象深い内容ですが、特に私が印象に残った点が次の2つです。
―市場で消費者が何を求めているか、それを知るためにマーケティングが行われ、それを受けて商品化、マーチャンダイジングが行われる。営業活動の中核はマーケティングだから、運送業界にマーケティングという考え方がないのはおかしい― 講演で聞いた「市場」という言葉が、私の心に強烈に焼きついた
多くの企業では、顧客接点がある営業マンが顧客の声を集め、その情報を社内で集約し、その集約した顧客の声からニーズを読み取って新サービスを考える組織があり、そういう役割を担う人がいます。いわゆるマーケティングです。しかし、マーケティングをきちんと組織している企業ばかりではありません。営業部長や営業課長、または一人ひとりの営業マンという個人に委ねている企業も少なからず存在します。このあたりは経営者の考え方に依存しますし、中堅企業においてはマーケティングという機能だけで一つの部門を組織するほどのジョブサイズがなかったり、人的余裕がなかったりします。
この小倉昌男氏の言葉を単純にとらえると、やはり企業にはマーケティング機能を持った組織を作るべきとの帰着になるかもしれません。ですが、それは表面的な理解ではないでしょうか。
仮に組織がなくとも、マーケティングの重要性を理解し、営業活動と並行してマーケティング活動が実践させることができれば、この教えに沿っているのだと考えられます。実際に同氏も「営業活動の中核はマーケティングだ」と述べており、”営業”と”マーケティング”を切り分けてはいません。
ただ、専門組織がない企業においては、営業部課長や営業マンは予算達成を至上命題に日々活動しているため、新商品や新サービスの種になる顧客ニーズの把握の優先順位が予算達成のための売り込みに劣後する可能性があります。ですので、ここを何らかの仕組みを導入し工夫できれば、”予算達成のために商品やサービスを売る活動”と”マーケティング活動”を”営業活動”として両立することができます。
例えば、新商品の約70%が世界初、業界初の商品と言われるキーエンスでは営業が「ニーズカード」に顧客ニーズを書いて、商品開発部隊に月に1件以上出します。これは単に顧客がこんなことを言っていたというものではなく、商談中に客が何気なく発した言葉が書かれることもあり、営業のヒアリング力とニーズカードの質が直結するようです。そして、ニーズカードの提出を促すためにインセンティブを設けています。顧客ニーズの把握という点では、非常に優れた仕組みで、ぜひマネしたい工夫ではないでしょうか。
話が他社に及びましたが、要はマーケティング専門の組織が必須ではないということです。自社がキーエンスでなくても、きっと工夫次第で乗り越えていけるはずです。
だいたい都市銀行とか地方銀行とか信用金庫とかいう区分は、大蔵省の都合で勝手に作ったものではないか。利用する側にしてみれば、どうしてそんな区分が必要なのかわからない。利用者の利便を考えれば、水平統合だけではなく、垂直統合があってもよいと思う
常に利用者(顧客)の視点で考えることの重要性を痛感させられる言葉です。組織のあり方や業界の構造は、誰のために、何の目的で存在するのかという根本的な視点です。
顧客視点の重要性を説き、既存の区分や規制に囚われず、顧客の利便性を最優先に考えるべきだいう主張ですが、これを読むと、自分が当たり前だと受け入れてしまっていることが、何と多いことかと考えさせられます。
これは経営者が既存の枠組みや常識に疑問を持ち、顧客価値を中心に据えた事業再構築を考える重要性を当時から示唆するものかもしれませんね。とても共感いたしました。
最後に
小倉氏は「経営は論理」が口癖で、「物事を情緒的に考える人は経営者に向かない」と言っておられたそうです。本書は、経営学に関する名著として名高く、読んでいて創業者である同氏のエネルギーを感じますし、とても共感させられる内容でした。
物流業界だけでなく、あらゆる業種のビジネスリーダーが学ぶべき普遍的な経営の知恵が詰まった一冊です。ぜひ手に取っていただければと思います。おすすめです!