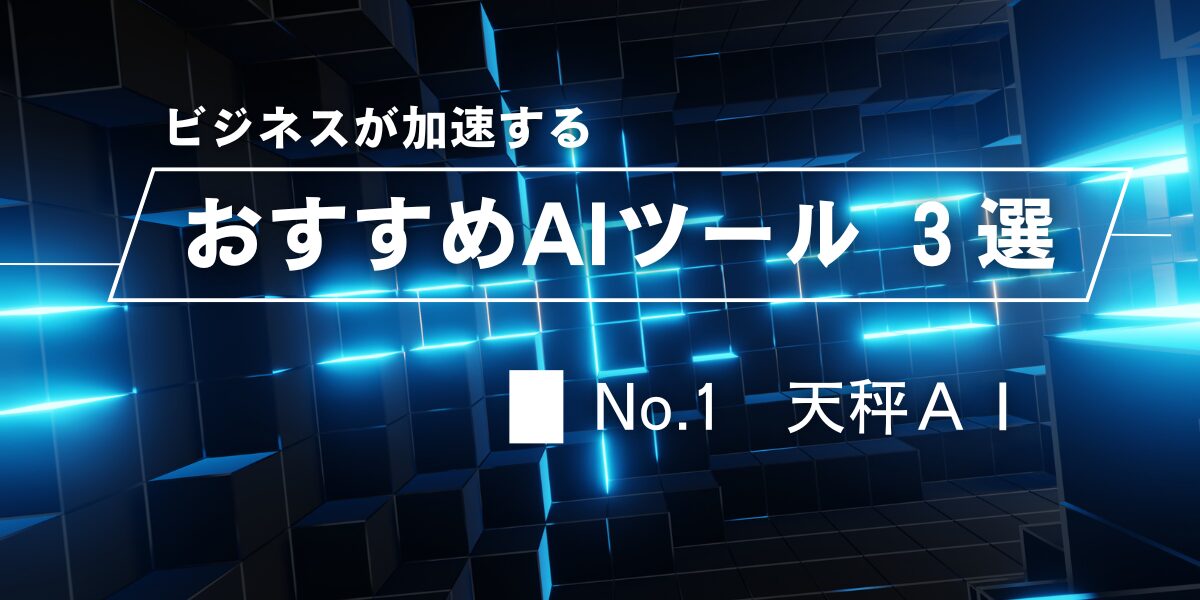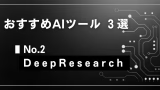リスキリングとは?
経済産業省の第2回 デジタル時代の人材政策に関する検討会に提出されているリクルートワークス研究所の資料「リスキリングとは―DX時代の人材戦略と世界の潮流―」によると、リスキリングは次のように説明されています。
新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_jinzai/pdf/002_02_02.pdf
そして、次のように補足・強調されています。
近年では、特にデジタル化と同時に生まれる新しい職業や、仕事の進め方が大幅に変わるであろう職業につくためのスキル習得を指すことが増えている
リスキリングは単なる「学び直し」ではない。昨今の「学び」への注目のなかには、個人が関心に基づいて「さまざまな」ことを学ぶこと全体をよしとする言説が多いが、リスキリングは「これからも職業で価値創出し続けるために」「必要なスキル」を学ぶ、という点が強調される
今回は、そんなリスキリングに関する企業の取り組み事例を調査し、現在、各社においてどのような取り組みがなされているのかをご紹介いたします。
結論
各社の取り組みを調べた結果、リスキリングに関する取り組みの代表例は、直接あるいは間接的な金銭的支援です。そして、各社ともいくつかの取り組みを複合的に実施しています。
特に直接的な金銭インセンティブの取り組みが多く、その事例は次でご紹介する5つに大別されます。
- 資格取得に要する費用の補助(受験料や通信教育費用)
- 特定の資格を対象としないeラーニング費用補助
- 資格取得時の一時金支給
- 資格取得後の手当支給
- その他
なお、今、企業は社員のリスキリング支援に注力しており、特にデジタルに関連するリスキリングが熱くなっていますが、取り組み内容を見ると必ずしもデジタルに限定しているわけではありません。
では早速、各社の取り組み事例をご紹介いたします。
直接的な金銭インセンティブ
①資格取得に要する費用の補助(受験料や通信教育費用)
社員が学習を始める際の初期費用負担を軽減する、最も基本的な支援策です。
②特定の資格を対象としないeラーニング費用補助
特定の資格取得に限定せず、社員が自身の興味やキャリア目標に合わせて幅広い分野の知識・スキルを習得できるよう、自律的な学習を支援します。
③資格取得時の一時金支給
資格取得という目標達成に対する明確なインセンティブとして機能し、社員のモチベーション向上と達成感を高めます。
④資格取得後の手当支給
取得した資格が業務に継続的に貢献することへの評価であり、社員の専門性維持・向上を長期的に促すものです。
⑤その他
・特定の資格を対象としない手当支給
リスキリングによって得られたスキル(例:特定のTOEIC®スコア、データ分析スキルなど)を評価し、給与に反映させる方法もあります。この場合、資格取得以外の学びについても社員のモチベーションを高める効果があります。
・リスキリング名目で手当てを支給
資格やスキルを特定せず、リスキリング名目で手当てを支給する取り組みも見られます。
各社の取り組み -事例紹介-
資格取得費用・eラーニング費用補助 / 一時金・手当支給
「資格取得奨励金」や「資格取得支援金」など名称は様々ですが、資格取得に要する(要した)費用の一部を補助する制度で、多くの企業で導入されています。
中でも直接的に受験料などの資格取得に要する費用を補助する制度と、eラーニングによる幅広い学習機会を提供する制度の二つを併用している企業が多く見られます。
なお、トヨタやソニーグループなど日本を代表する企業でも様々な制度が設けられていますが、日経225に採用されているような超大手よりも中堅企業を中心にご紹介します。また、幅広く参考となるように、業界を絞らず様々な業界から事例をピックアップしています。
・株式会社フォーカスシステムズ (証券コード: 4662)
官公庁・自治体向け、医療機関向けなどのシステム開発、組込みソフトウェア開発などを手掛ける企業で、同社では、情報処理技術者試験、医療情報技師、各種ベンダー資格など、業務に必要な資格の取得費用を補助し、資格取得時に報奨金を支給しています。
・株式会社TOKAIコミュニケーションズ (証券コード: 2486)
光ファイバーネットワークを基盤とした通信サービス、データセンター事業などを展開するTOKAIホールディングス傘下の企業で、同社では、電気通信工事施工管理技士、情報処理技術者試験、ネットワーク関連資格など、業務に必要な資格の取得費用を補助し、資格取得時に一時金を支給する制度があります。
・株式会社日特建設 (証券コード: 1929)
地盤改良工事、トンネル工事、ダム工事など、特殊な土木工事や基礎工事を得意とする専門建設会社で、同社では、1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、RCCM(シビルコンサルティングマネージャー)、技術士、測量士などの国家資格の受験料補助や合格時の報奨金支給を行っています。
・株式会社日本管財 (証券コード: 9792)
総合ビル管理サービスの同社では、建築物環境衛生管理技術者、電気主任技術者、電気工事士、ボイラー技士、消防設備士、エネルギー管理士、宅地建物取引士、マンション管理士など、ビル管理・不動産関連の多岐にわたる資格について、受検料や通信教育など資格取得に要する費用の補助を行うほか、合格時の報奨金支給や資格手当の支給を行っています。
・株式会社オープンアップグループ (証券コード: 2154)
建設・プラントエンジニアリング人材サービスを展開する同社では、建築士、施工管理技士(建築・土木)、宅地建物取引士など、建設関連の国家資格に対して、資格取得時に祝い金に加え、毎月の資格手当を支給する制度があります。
・日東紡績株式会社 (証券コード: 3110)
グラスファイバーなどの化学工業製品の製造・加工・販売を行う同社では、社員の専門性向上を目的とした資格取得支援を行っており、合格時に奨励金を支給する制度があります。
・因幡電機産業株式会社 (証券コード: 8150)
電設資材、産業機器などの卸売を行う同社では、業務に関連する電気工事士、施工管理技士などの資格取得を支援し、報奨金を支給しています。
・株式会社ハローズ (証券コード: 2742)
中国・四国地方を地盤としてスーパーマーケットを展開する同社では、販売士(リテールマーケティング)などの資格取得を奨励しており、入社後に販売士を取得した社員に対し、合格級に応じて合格祝金だけでなく、資格手当を支給しています。また同社では正社員だけでなく、パートタイム勤務者にも資格手当を支給している点が特徴的です。
・株式会社ZOZO(証券コード: 3092)
ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは日経225構成銘柄ですが、珍しい取り組みをされているのでご紹介します。
同社では、全正社員を対象にリスキリングなどに使える日々進歩手当という名前の手当を設けています。
社員の「日々進歩」を後押しする手当として、これまでビジネス部門の社員を対象に自己成長を目的に毎月支給されていた自学手当を、支給範囲を全社員へ拡大。在籍期間が半年経過するごとに2,500円ずつ、最大10万円まで増額。
自己学習費用として手当を支給する(しかもMAX10万円も!)ケースは珍しく、ユニークな取り組みになっています。
注目のデジタルスキル
リスキリングで注目されている分野はデジタルスキルです。
デジタルスキル標準(DSS)
2022年12月に経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が「デジタルスキル標準(DSS)」を策定・公表しました。
「デジタルスキル標準(DSS)」は、DXに関してすべてのビジネスパーソンが身に付けるべきスキル・マインドを定義した「DXリテラシー標準(DSS-L)」と、DXを推進する人材の役割(ロール)や習得すべきスキルを定義した「DX推進スキル標準(DSS-P)」で構成されています。
G検定
デジタルスキルの中でも、特に注目されている分野はAIです。
そして、各社が取得を奨励している「G検定」は注目です。
G検定とは、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する、AI・ディープラーニングの活⽤リテラシー習得のための検定試験です。 AI・ディープラーニングに関わる全ての方が受験対象です。 AI・ディープラーニングについて体系的に学ぶことで、「AIで何ができて、何ができないのか」「どこにAIを活用すればよいか」「AIを活用するためには何が必要か」が理解でき、データを活用した新たな課題の発見やアイデアの創出が可能になる、デジタル施策の推進に自信が持てるようになるなど、あなたのビジネスやキャリアの可能性が飛躍的に広がります。
https://www.jdla.org/certificate/general/
「医療用医薬品」に特化した創薬会社である中外製薬(証券コード: 4519)は日経225構成銘柄です。同社ではデジタルグループ会社を含めた全社員を対象にG検定の受験を推奨しており、受験費用を支給しています。3年間で500名以上の合格者を輩出するなど、積極的な推進を行っています。
他にも情報システム、樹脂・エレクトロニクス、化学品等の事業を展開する三谷産業(証券コード:8285)や総合建設業の清水建設 (証券版コード:1803)もG検定の取得を奨励しています。
そういえば、つい先日も総合商社の三菱商事(証券コード:8058)がAI資格を管理職の昇格要件にし、いずれは役員を含む全社員に資格取得を義務付けるという報道が出ていました。
やはりこの分野に関するリスキリングの注目度は大変に高いものがあります。
その他のリスキリング支援の切り口
これらの5つのタイプは「直接的な金銭支援」という側面に焦点を当てました。ただ、リスキリング支援には、多様な切り口があります。
間接的な金銭支援
・株式会社LIFULL (証券コード:2120)
「LIFULL HOME’S(ライフル ホームズ)」 を運営し不動産情報サービス事業を行う同社では、社員のスキルを評価に反映する仕組みを構築することで、リスキリングを支援しています。直接的ではなく間接的金銭支援といえるかもしれません。
LIFULLでは、職種ごとに「この等級であればこのくらいの成果を上げてほしい」という基準を設け「スキルマップ」として全社に公開し、このスキルマップと評価が連動させることで、結果的に成果を上げるためのスキルの獲得にモチベーションが発生する仕掛けになっています。
なお、このスキルマップは、LIFULLのみで期待される成果や能力ではなく、広く労働市場において求められるスキルも勘案して作成しておられるようです。
社内研修・学習機会の提供
自己学習の印象が強いリスキリングですが、冒頭でご説明した通り、リスキリングとは“新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること”であり、“させること”もリスキリングに含まれます。
つまり、企業内研修もリスキリングの一つの切り口になります。
業務時間内での学習支援(時間的配慮)
例えば、企業が求める新しいスキル(例: AI・データサイエンス、DX推進、新規事業開発など)を学ぶための社内研修プログラムや専門講座を自社で提供するケースが考えられます。
社員が業務時間の一部を使って学習に取り組めるよう、時間的な余裕を確保するということが考えられます。
アウトプット機会の提供・キャリアパスの提示
資格取得や学習で得た知識・スキルを実際に業務で活用できるプロジェクトや部署への異動機会(ジョブローテーションなど)を設けることも考えられます。
また、リスキリングによってどのようなキャリアパスが開けるのかを社内で提示し、社員の学習意欲を高めるというとる君もあり得るでしょう。1on1ミーティングやキャリアカウンセリングを通じてキャリア相談に乗ることも、リスキリングを促進する取り組みの一環といえるかもしれません。
まとめ
リスキリングに関する取り組みの代表例は、直接あるいは間接的な金銭的支援です。
ただ、他にも社内研修・学習機会の提供、業務時間内での学習支援(時間的配慮)、アウトプット機会の提供・キャリアパスの提示といったアプローチがあります。
今、企業は社員のリスキリング支援に注力しており、特にデジタルに関連するリスキリングが熱くなっていますが、もちろんリスキリングとはデジタルに限定したものではありません。
人材のリスキリングは、VUCAや人的資本経営の文脈ならずとも、企業が成長していくうえで注力すべきテーマで、各社とも複数の施策を採用してリスキリングを後押ししています。
リスキリング促進の制度設計においては、いくつかの取り組みを複合的に組み合わせて、多角的なアプローチで社員のリスキリングを後押しできると良いでしょう。
小出しにするよりも、一気呵成に取り組んだ方が会社の本気度が伝わりますし、従業員にとって活用しやすい施策となります。結果として取り組み効果も上がると考えられます。