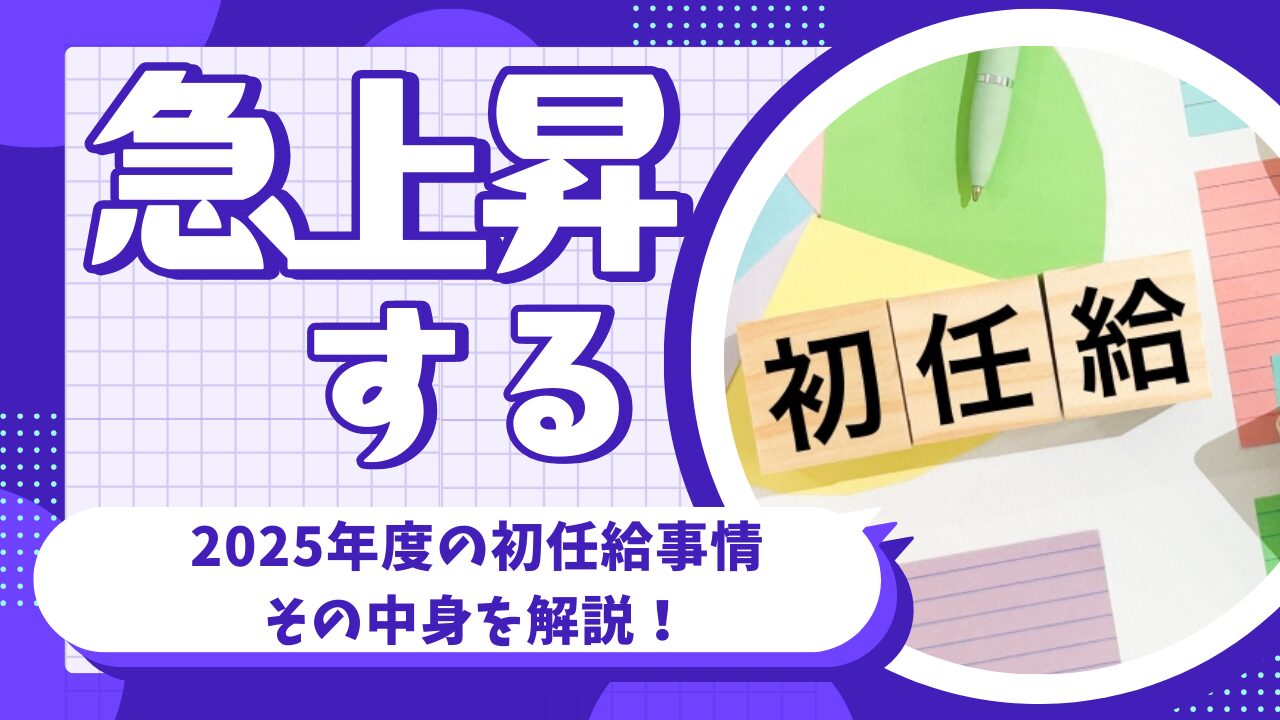人手不足と物価上昇による初任給の上昇
正社員・非正社員を問わず人手不足を感じている企業が増えています。ここに物価上昇も相まって、各社ともこぞって賃上げを行っており、さながら賃上げ競争と言っても良いような様相です。
物価については、総務省の「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)3月分及び2024年度(令和6年度)平均」の「第5表ラスパイレス連鎖基準方式による消費者物価指数(参考指数)(全国)」によると、2025年3月の総合指数は111.3でした(2020年を100としています)。
マクドナルドの「ビッグマック®」の価格も、1990年代は380円でしたが、2025年4月時点で480円と1.26倍になっていますし、お米の価格上昇も耳目を集めています。
生活者目線でも、確かに物価上昇を実感させられます。
また、帝国データバンク(https://www.tdb.co.jp/)が2025年2月20日に発表した「2025年度の賃金動向に関する企業の意識調査」では、次の通り説明されています。
2025年度における正社員の賃上げ実施を見込んでいる企業の割合は、61.9%だった。その内訳を雇用過不足感別に比較すると、人手不足を感じている企業では68.1%にのぼり、全体を大きく上回った。その他、「適正」が58.3%、「過剰」が51.9%だった。
当調査は毎年1月に実施しており過去の推移をみると、2020年度以前は6割をやや上回る水準で推移していたものの、コロナ禍による業績悪化で人件費の上積みが難しくなったことが影響し、5割台に低下。そうしたなか、2023年度は飲食料品や日用品の値上げが相次いだことを受けて賃上げ機運が高まり、79.8%まで上昇。そして2025年度の見込みは、前年度比+2.2ptの68.1%となり、足元ではコロナ禍以前を上回る賃上げ機運が生じているといえる。
現在の経営では、初任給をはじめとする賃上げが、人材の確保・定着に向けた大きなテーマになっています。これは大企業のみならず、中堅企業や中小企業も同様です。
何とか賃上げの原資を確保して賃上げを実現しなければ、他社比較で処遇差が拡大していくことになります。そうすると、退職者は増加する一方で採用難は全く改善されず、中小企業においては「人手不足倒産」のリスクが高まってくるでしょう。
そしてこの賃上げは、売り手市場による採用競争の激化を背景として、特に新卒新入社員の初任給に顕著に現れています。
例えば、ダイワハウスでは2025年4月の大卒初任給を従来の25万円から35万円に引き上げることを発表しています。初任給の10万円UPは、上昇率40%という凄まじい水準の引き上げになっています。
三井住友銀行でも、2026年4月から大卒初任給を30万円に引き上げることとしています。現行水準からの引き上げ幅は4万5000円で上昇率は17.6%になります。
これらの動きを受けて、巷では「初任給30万円時代」などとも言われるようになってきています。
初任給とは?
そもそも初任給とは何でしょうか?
厚生労働省の賃金構造基本統計調査における「初任給」の定義は次の通りです。
通常の所定労働時間、日数を勤務した新規学卒者の令和元年6月分の所定内給与額(所定内労働時間に対して支払われる賃金であって、基本給のほか諸手当が含まれているが、超過労働給与額は含まれていない。)から通勤手当を除いたものである。
つまり、残業代と通勤手当以外の新規学卒者の賃金ということです。
初任給=基本給というイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか?
ですが、初任給=基本給ではありません。
実際に、各社の初任給には基本給以外の賃金を含んでいるケースがあります。
初任給引き上げの中身
上記の通り、大幅上昇している初任給ですが、基本給の上昇と合わせて基本給以外の支給も多様化しています。そのため、企業が募集要項に記載している初任給を額面通り捉えてしまうと思わぬ落とし穴にハマってしまう危険があります。
従来以上にしっかりと内訳を確認することで、誤解なく正確に理解することが重要です。
初任給が基本給だけではないことを踏まえたうえで、ここでは基本給以外で初任給を構成する賃金にどういったものが存在するのかを見ていきたいと思います。
代表的なものをご説明いたします。
1.固定残業代込み
固定残業代込みとは、実際の勤務時間にかかわらず、一定時間の固定残業代が基本給に加算され、基本給と固定残業代の合計額を初任給としているケースです。
固定残業代のメリット
一般的に、会社にとっては固定残業代を支給することで長時間労働を抑制し、労働生産性の向上を促す効果があります。また、変動要素である残業代の一部が固定化されるため、予算を立案しやすくなったり、人件費の変動幅を小さくする効果があります。加えて、賞与計算の元になる基本給を抑制する効果もあります。
社員にとっては、残業時間が少なくても、固定残業代を受け取れるため、収入が安定します。また、実際の勤務時間にかかわらず、残業代が固定で支給されるため、より短い時間で仕事を終えたいというモチベーションになります。その結果、残業時間が短縮されると退勤時間が早くなり、プライベートの時間が増えることになります。
固定残業代の事例
例えば、東証プライム上場の塩野義製薬の大卒初任給は255,000円で、この内訳は”基本給+15時間裁量給の合計+ワークスタイル手当”となります。
同社では裁量給という15時間に相当する残業代が固定残業代として支給される仕組みになっており、この裁量給として22,160円が基本給に加算されています。
また、ワークスタイル手当という名称の手当も初任給に含まれています。同社のワークスタイル手当とは、在宅勤務時の環境整備費・光熱費、出社時に発生する食事代等の諸費用の補助として支給する手当とされ、一律10,000円になっています。
つまり単純計算で、初任給255,000円から裁量給22,160円とワークスタイル手当10,000円を控除した222,840円が基本給という計算になります。
2.諸手当込み
諸手当込みとは、基本給に確定拠出年金や家賃補助などの各種手当を加算し、基本給と諸手当の合計額を初任給としているケースです。
初任給に内包される諸手当の例
初任給に内包される代表的な諸手当として、次の3つをご紹介いたします。
・ライフプラン手当
選択制の企業型確定拠出年金(選択制DC)を導入している企業における確定拠出年金の掛金相当額が代表例の一つです。
企業によって名称は異なりますが、ライフプラン手当・ライフサポート手当・ライフデザイン手当などと呼ばれます。
この手当は確定拠出年金の掛金相当として支給されている点に注意が必要です。選択制の企業型確定拠出年金は、従業員が掛金を拠出するかどうかを決定できるため、掛金を拠出しなければ給与として受け取ることができますが、掛金として拠出することをを選択すると給与として受け取ることはできません。
・住宅手当
住宅手当とは、従業員が支払っている家賃や住宅ローンなどの住宅費用を補助することを目的として支給される手当です。
現在ではパートタイム・有期雇用労働法等を根拠にした同一労働同一賃金で、雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保することを求められており、これを受ける形で支給する企業は微減傾向にありますが、全員が総合職で転勤義務を負う企業などをはじめ、大企業では住宅手当を維持している割合が高くなっています。
また、住宅手当は初任給に含めている企業もあれば、初任給に含めていない企業もあります。そのため、初任給に含まれていなくても、住宅手当を支給している企業があることに注意が必要です。
・地域手当
地域手当とは、物価が高い地域に勤務または居住する従業員に支給される手当です。東京都近郊や京阪神地方など、他の都市に比べて物価が高い地域に勤務または居住する従業員の実質所得の均衡を図ることを目的としています。
地域手当の他、都市手当とも呼ばれます。
諸手当込みの事例
例えば、INPEXでは、大卒初任給が394,800円になっており、この金額には1都3県(東京・埼玉・千葉・神奈川)に住む場合の住宅補助50,000円とライフプラン手当25,000円が含まれています。
また、資生堂では大卒初任給が237,890円になっており、この金額には東京都23区内で勤務する従業員に対して支給される地域手当9,000円を含んでいます。
ディスコでは、社員が「自身の価値創出」と「周囲との信頼関係」の継続性を自己評価し、自信がある場合はコミットすることで基本給に10万円が加えられるコミット手当が初任給に含まれていますし、良品計画では従業員特別手当という名称で20,000円が初任給に含まれています。
各社とも東証プライム上場の大企業で、様々な手当を初任給に含めています。
注意が必要なケース
初任給は企業選びの重要な要素です。会社選びにおいて、給与を重視される学生の方も多いでしょう。ですが、高い初任給にひかれて入社したけれど、思っていたほど年収が伸びないというケースも存在します。
こうならないよう、次は注意が必要なケースを3つご説明します。
入社後数年間、昇給しない
高い初任給に惹かれて入社したけれども、入社後、数年間昇給しないというケースがあります。あるいは昇給するけれども、昇給額が非常に小さいというケースが存在します。
初任給の引き上げは単年の傾向ではなく、ここ数年の傾向です。つまり、連続して初任給を引き上げている企業も多く存在します。毎年のように初任給を引き上げていると、企業にとっても徐々に引き上げ原資を確保することが難しくなってきます。
そこで2年目や3年目の昇給を先食いする形で、初任給を引き上げるのです。
こうすると、会社にとっては人件費増の影響を緩和することができます。
他にも人件費増の影響を抑制する方法として、昇給幅を小さくする方法があります。
例えば、年1回の昇給時に標準考課で6,000円昇給していたところを、3,000円に変更するわけです。このように昇給ピッチを小さく刻むことで、役職ごとや年次ごとの基本給水準を大きく変更せずに、初任給だけを引き上げることができます。
当然ですが、大企業でも無尽蔵に初任給を引き上げることはできません。中小企業は初任給の引き上げ自体が苦しいですし、中堅企業においても企業ごとに明らかな差がついてきています。そうすると、このように初任給引き上げによる人件費増を少しでも抑制しようと、様々な方法で工夫する企業が出てきてもおかしくありません。
ただ、入社後の昇給の実態については、採用HPの募集要項を見ても分かりません。学生の皆さんはOB・OG訪問時に在籍社員に聞くか、説明会などで人事担当者に質問するしかありません。
初任給が高いからといって、その後の昇給も高くなるとは限りません。
初任給の高さと入社後の昇給額は必ずしも一致しないことにも注意を払いたいところです。
年俸制
季節賞与や決算賞与を支給する会社が多く、この場合、月給+賞与の合計が年収になります。賞与支給額は会社業績や労使交渉によって決定されますので、月給の何ケ月分が賞与として昇給されるのか、事前に確定していません。いわゆる月給制と呼ばれる支給方法です。
ところが、年俸制の企業の場合、年収が先に決定され、それを12分割して支払われます(あるいは月給制企業の賞与支給月や期末月に厚く支給するため14分割する企業もあります)。
仮に月給制の企業と年俸制の企業では、年収が同じでも、支給方法の違いによって月給に差が生じます。年俸制の場合は年収を”12ケ月”で割りますが、月給制の場合は年収を”12ケ月+賞与月数”で割りますので、月額では年俸制の方が多くなるという仕組みです。
年俸制は、社員にとっては年収が事前に確定するため収入が安定するというメリットがありますが、上記のように同業他社との比較で初任給が高くても、想定年収では逆転する場合があります。
社会人経験がある方は月給制と年俸制の違いを理解されていると思いますが、学生の方にとっては分かりにくいかもしれません。
これは人事担当者が他社の初任給情報を調査する際も同様です。対象会社が月給制か年俸制かに注意しないと、思わぬミスリードを生むことになりかねません。
月給は上昇しているが、賞与が減少
一般的に、賞与には支給月数や業績月数などと呼ばれる係数が存在します。そして賞与計算においては、月給×支給月数〇ヶ月分というように計算します。
例えば月給25万円で夏の賞与が2.0ヶ月分なら、50万円が賞与支給額になるというわけです。
こういった計算方法なので、月給が上昇すると賞与も上昇することが一般的です。しかし、それだと企業は人件費増のインパクトが大きくなりますので、支給月数を調整している場合があります。
つまり、月給を上昇相当額を賞与から削って、企業の人件費負担を緩和しているのです。
人件費負担が重い企業の中には、ベースアップを行って月給は引き上げたけれども、月給の引き上げと同額が賞与から削られ、結局、年収ベースでは変化がなかったなんて話も聞きます。
初任給だけで判断せず、年収ベースでの変化についても情報収集するようにしましょう。
まとめ
少子高齢化が加速するなか、大企業では30万円を超える初任給も増加しており、初任給引き上げの流れは加速しています。この流れについていけない中堅企業や中小企業での人材確保は、ますます困難になりそうです。
初任給に固定残業代を含んだり、様々な手当てを加算して初任給と表現しているのは、初任給引き上げによる人材の囲い込みが強まる中で、如何に自社の条件が良いかをアピールするために各社が知恵を絞った結果ともいえます。
従来、日本企業の初任給は横並びで、企業間で大きな差はありませんでしたが、これからは業界ごと、そして企業ごとで初任給格差が鮮明になっていくでしょう。
その過程で、初任給も様々な賃金が組み合わされ、ますます多様化が進むことが予測されます。
そのため、各社の採用HPの募集要項で説明されている初任給について、その額面だけなく、基本給がいくらで、その他の賃金がいくらなのかという内訳をしっかりと確認しておきたいところです。
また、最後にご説明した昇給額の変更や月給制と年俸制の違いなど、賃金制度全体に関する理解が求められるケースも増加していく可能性があります。
横並びが崩れるということは、学生の方にとっても、自社の初任給水準について他社比較を行う立場である企業の人事担当者にとっても、わかりにくくなるということに他なりません。
単に初任給の額面に踊らされないよう、しっかりと情報収集を行うことが、今まで以上に重要になっています。