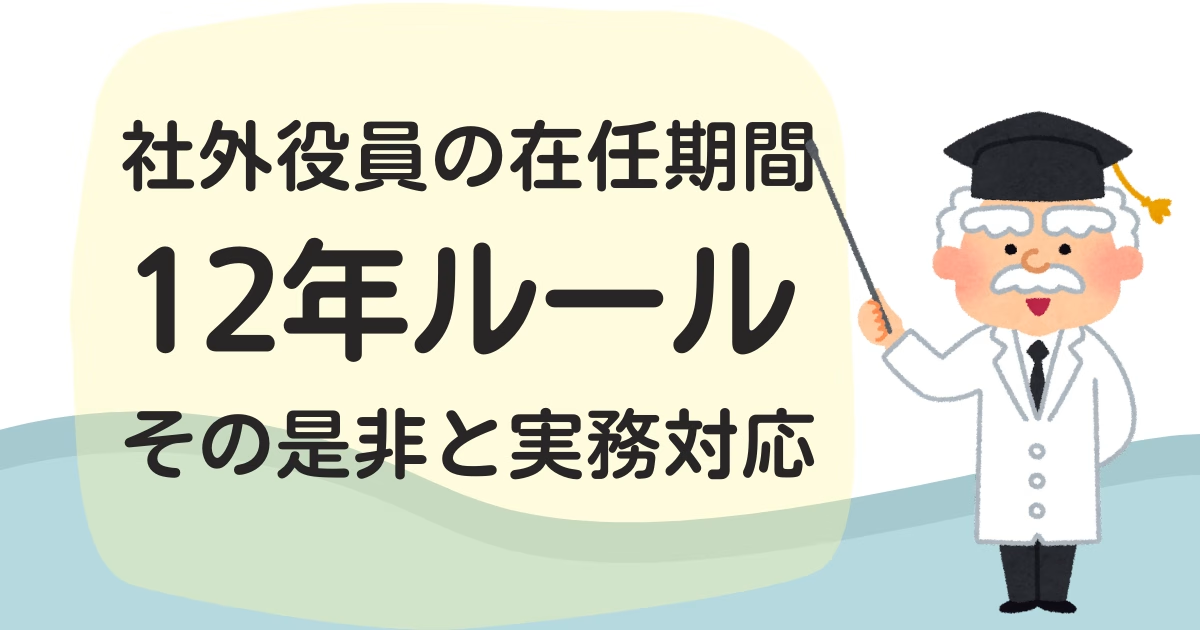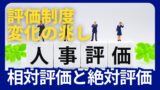現代の取締役会に対する要請
ISSや三井住友トラスト・アセットマネジメントなど国内外の主要な議決権行使助言会社や機関投資家が、在任期間「12年以上」の社外役員に対して独立性が欠如するとして反対を推奨する基準を設けました。
しかし、その合理性や実効性について疑問を感じたことはないでしょうか?
私は、社外役員の在任期間に対する上限を設けるという考え方は理解できるものの、あまりに実務家の感覚から乖離している基準であると感じています。
この「12年」という在任期間制限は、形骸化した取締役会から株主価値を守るうえで不可欠な基準なのか、それとも、それが本来高めるべき実効性を損なう形式的で画一的な投資家の道具に過ぎないのか、本稿ではこの問いに向き合います。
まず投資家が「12年」という基準を設けた背景を検討し、次に長期在任がもたらすデメリット・メリットを比較し、最後に在任期間制限を乗り越え、取締役会の実効性を確保するための方策を検討していきたいと思います。
投資家の論理 長期在任のデメリット
社外役員の在任期間に関する方針一覧
まず、主要な議決権行使助言会社・機関投資家の社外役員に関する方針を一覧にしました。
| 在任期間基準 | 基準の適用対象 | 基準導入の理由 | 基準抵触の場合の対応 | |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12年以上 | 監査に関与する社外役員 | 独立性の喪失 | 全社外役員一律の反対推奨ではなく、監査に関与する社外取締役の独立性に懸念がある場合に限り、候補者に反対を推奨(社外監査役・社外取締役(監査等委員)) |
| グラスルイス | 連続12年以上 | 社外取締役・社外監査役 | 取締役会の新陳代謝 | 取締役会議長等に反対を推奨、 ただし、社外取締役全員または社外監査役全員が連続12年以上在任の場合 |
| 野村アセットマネジメント | 12年以上 | 社外取締役 | 独立性の喪失 | 候補者に原則反対 |
| 大和アセットマネジメント | 12年以上 | 社外取締役・社外監査役 | 独立性の喪失 | 候補者に反対 |
| 在任期間基準 | 基準の適用対象 | 基準導入の理由 | 基準抵触の場合の対応 | |
|---|---|---|---|---|
| 英国CGコード | 9年 | 社外取締役 | 独立性の喪失 | Comply or Explain |
| ブラックロック(米国) | 短期・中期・長期の在任期間の組み合わせが不十分 | 特定の取締役 | 取締役会の新陳代謝 | 候補者に反対 |
グローバルスタンダードとしての取締役会の新陳代謝
取締役会の新陳代謝を重視する動きは、世界的な潮流と軌を一にしています。
- 英国の先行事例:9年ガイドライン
英国のコーポレートガバナンス・コードでは、9年を超える在任期間は独立性を疑わせる要因となると長年規定されてきました。
「Comply or Explain」の原則に基づき、例外を許容する柔軟性を持ちながらも、取締役会に新たな視点や知見を取り入れることの重要性を示しています。 - 米国の潮流 ブラックロック:取締役会の「構成バランス」重視
世界最大の資産運用会社であるブラックロックは、取締役会が「短期・中期・長期の在任期間の取締役の組み合わせが不十分」である場合に特定の取締役に反対するとしています。同社は、個々の取締役の在任年数そのものよりも、取締役会全体としての構成と新陳代謝の仕組みにあります。
ブラックロックの動きも加味して考えると、在任期間上限を設ける方向性と、取締役会全体としての新陳代謝を重視する方向性の二つがあります。
私は、新陳代謝を重視する方向性の方が、取締役会の実効性を確保することに実質的に貢献するものと考えます。単に形式的に12年が経過しているから一律反対というのは、特に社外役員候補の選定に苦労する中堅企業の実務家からすれば、やはり乱暴に感じてしまいます。
個人という”人”にフォーカスするのではなく、取締役会という”組織体(機能)”にフォーカスする方が合理的で実践的でしょう。
長期在任のデメリット
このように、社外役員の在任期間に上限を設けるという考え方の根底には「独立性」があり、議決権行使助言会社と機関投資家が長期在任基準を設ける理由は、この「独立性の喪失」という点にあります。
確かに「独立性」とは、社外役員を選任する大きな価値です。
特に社外取締役には、経営陣から独立した立場で株主の代理人として経営を監督し、必要であれば異議を唱えることが期待されているため、長期在任に伴う「独立性喪失」を理由とする反対推奨には理解できる部分があります。
長期在任がもたらすデメリットは確かにリスクとして存在します。
具体的には次の通りです。
- 心理的バイアス
永きにわたり同じ企業の経営陣と共に意思決定をしてきた社外取締役は、無意識のうちにその経営陣と心理的な一体感を形成する可能性があります。その結果、過去の判断を自己否定することになるような厳しい指摘や、経営方針の根本的な転換を求めることが困難になる「認知的不協和」や「グループシンク(集団浅慮)」といった心理的バイアスに陥るリスクが高まります。 - 経済的依存
社外役員の報酬が、本人の主たる収入源でなくても、社外役員という地位に伴う名声や経済的利益は、経営陣との対立を避けるインセンティブになり得ます。特に現経営陣が再任を推薦することを考えると、社外役員を維持したいという気持ちが、社外役員の鋭さを鈍らせる可能性は否定できません。 - 取締役会の形骸化
長期在任に伴う弛緩または友好的な雰囲気で進む取締役会は、経営陣にとって心地のよい、いわば馴れ合いの会議体になってしまうリスクがあります。このような取締役会には、その実効性を望むべくもありません。 - 社外役員の同質化
長期在任に伴い、社外役員が社内役員の価値観に触れる機会が多くなると、社外役員の価値観が社内役員と似通って、取締役会全体の価値観が同質化してしまうリスクがあります。
そうなると多角的な検討に基づく経営判断ができず、思わぬリスクを抱え込むことになりかねません。
長期在任のメリット
では、長期在任にはデメリットしかないのでしょうか。
そんなことはありません。
在任期間の長期化に伴って、社外役員には知見が蓄積されます。その蓄積が取締役会の実効性向上につながると考えるからこそ、一律の在任期間制限に疑問が生じるのです。
長期在任のメリットは次の通りです。
- 深い事業理解による実効性の向上
永きにわたり同じ企業の監督・監査に関与してきた社外役員には、その企業のビジネスモデル、競争環境、組織文化、そして成功と失敗の歴史といった、一朝一夕では得られない文脈的知見が培われます。
これらの知見は、M&Aなどの事業再編・新規事業開発・人材開発など、短期的でない中長期的な企業価値向上の課題に関して、その企業に適した有意義な助言や実効的な監督を行う上でとても貴重な要素といえます。 - 信頼に基づく建設的な対話
信頼関係は、より率直で建設的な議論を可能にしますが、信頼関係の構築には時間を要します。したがって、一定以上の在任期間は、経営陣と社外役員との信頼関係の構築に寄与する側面があると評価できます。
社内役員も胸襟を開いて率直に協議し助言を求めることができる関係性は、取締役会の機能を高める上で有効です。 - リスク監視能力の向上
その企業の歴史と事業運営を深く理解している取締役は、新たに出現したリスクの兆候を早期に察知し、経営陣が提示する対策の妥当性を的確に評価する能力に長けているといえます。 - 積み重ねた知見があるからこそ、今までの文脈を踏まえた実効力のあるリスク監視が可能になります。
トレードオフ問題
上記の通り、長期在任にはメリット・デメリットのいずれも存在します。つまり、長期在任を支持する主張と、それに警鐘を鳴らす主張には、どちらも正当な理由があります。
したがって、どちらか一方が正しく、他方が間違っているという二元論では整理できません。
最適な在任期間とは、固定された年数ではなく、「逆U字カーブ」を描くものと考えられます。つまり、社外役員への就任後数年間は、経験の蓄積とともに実効性が急速に高まるが、ある時点を過ぎると、今度は独立性低下のリスクが、蓄積された知識のメリットを上回り始めると考えるのが妥当で、この点に異論はないでしょう。
つまり、この問題に関して一番重要なこと、実務家として優先すべきことは、どちらの主張が正しいかを証明することではありません。
長期在任がもたらす「リスクを最小化」しつつ、知見の蓄積がもたらす「メリットを最大化」するためのガバナンス体制をどう構築するかこそが、本当に取り組むべきテーマとなるべきです。
取締役の評価という根本的な問題
在任期間を巡る議論が不毛な対立に陥る根本的な原因は、多くの日本企業において、取締役一人ひとりのパフォーマンスを客観的かつ定量的に評価し、それを役員指名に反映する仕組みが存在しないことです。
先進企業では取締役会全体の実効性評価を行っていますが、多くの企業ではまだ道半ばというのが実態です。指名報酬委員会など任意の委員会を設置し、取締役個人の評価を報酬や指名に反映する企業は増えてきていますが、報酬はともかく、指名に反映している企業は多くはないでしょうし、また社内役員を対象としても社外役員までを対象としているケースは稀でしょう。
問題点
投資家は、より高度で信頼性の高い評価軸(パフォーマンス)が存在しないため、単純で測定可能な代理指標(在任期間)を用いざるを得ないという側面があります。
取締役の再任が、その在任期間ではなく、実証された貢献度に基づいて判断されるのであれば、そもそも在任期間基準は生まれなかったかもしれません。
解決策
企業は、取締役個人のパフォーマンス評価制度を導入し、そのプロセスと結果の透明性を確保すべきです。
- 評価基準の策定
「優れたパフォーマンスとは何か」の具体的な定義が必要です。
例えば、取締役会への出席率といった定量的な指標に加え、専門的知見に基づく助言の質と数、社内役員への建設的な発言の質と数、さらにはガバナンス体制の改善への貢献といった定性的な側面も考慮されるべきでしょう。 - 適切なプロセスの実行
評価は指名委員会または筆頭独立社外取締役が主導し、取締役同士の相互評価(360度評価)や自己評価を組み込むべきです。
客観性を高めるために、外部の専門機関を評価プロセスに活用することも有効な選択肢ですが、大企業はともかく中堅企業以下ではここにコスト投下することは難しいでしょう。 - 評価と再任の連動
評価結果は、該当者へのフィードバックに留まらず、取締役会や指名委員会が当該取締役を次期株主総会で再任候補者とするか否かを決定する際の、最も重要な判断材料とすることで、問題は解消します。
例えば、在任13年の社外取締役が依然として良質なパフォーマンスを提供できていることを評価によって証明できれば、在任期間の長短という基準は不要になり、その時点で議論は終了します。
良質なパフォーマンスがあり企業価値向上に貢献できているなら、むしろ当該社外役員の任期を12年で終えることの方が不合理ではないでしょうか。
中堅・中小上場企業の現実的課題 人材確保の難しさ
さてもう一つ、中堅・中小上場企業には理論とは別の現実的な問題点として「人材確保の難しさ」が存在します。
大企業とは異なり、中堅・中小規模の上場企業にとって、社外取締役の在任期間制限は、後任の人材確保が難しいという、極めて現実的な問題を生じさせます。
- 候補者プールの枯渇
そもそも経営に関する深い知見と経験を持ち、かつ独立性の要件を満たす社外取締役候補者の絶対数が限られています。
特にプライム市場上場企業を中心に社外取締役の設置・増員が進む中で、有能な人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。
社外監査役は、社外取締役に比べると幾分マシでしょうが、それでも難易度が高いことは否めません。 - 報酬と「相性」のミスマッチ
社外役員の報酬相場は分散しており、中堅・中小企業は大企業と同水準の報酬を提示することが難しい場合が多いのが実情です。
また、報酬の問題をクリアできたとしても、自社の事業内容や企業文化との「相性」が合う候補者を見つけることはさらに困難といえます。
ビジネスに対する考え方や方向性が大きく異なる人材を招聘した場合、取締役会の議論を混乱させ、意思決定の足を引っ張るリスクも存在します。
このような人材確保の難しさが、結果として、現任の社外取締役に可能な限り長く在任してもらいたいというインセンティブを生み、長期在任問題の構造的な要因になっている側面もあります。
実効的な取締役会構築のために
最後に、実効的な取締役会構築のための方策をまとめます。
- 取締役会構成における「ポートフォリオ・アプローチ」の採用
個々の役員を独立して評価するのではなく、取締役会全体をスキル、経験、そして在任期間の「ポートフォリオ」として構成する視点を持つべきです。
長期在任の知見と新任者の新鮮な視点が健全なバランスで共存できれば、取締役会全体としての実効性は確保されます。
要はブラックロックのアプローチと同様で、取締役会会長や指名委員会は、ここにこそ注力すべきです。 - 取締役個人のパフォーマンスを適切に評価する
社外役員を含む全ての役員を対象とした、パフォーマンス評価制度の導入・運用が、取締役会の実効性確保・向上の重要なポイントになります。すべての役員が難しければ、少なくとも取締役には導入すべきです。
これまで検討してきた通り、個々のパフォーマンスこそが重要で、この評価結果を役員指名に反映することで、実効的な取締役会運営に如何に”貢献”しているのかを明確にします。そして、評価プロセスと結果概要を透明性高く開示することで、投資家の信頼を醸成します。 - 「エクスプレイン(説明)」を恐れない
未だ「説明」を失敗と捉える風潮があるかもしれませんが、エクスプレインはコンプライの失敗ではありません。
現在の自社に合わせて最適化した、形式的でない実質的なガバナンス体制を構築した姿は一様ではなく、必ずしもコーポレートガバナンスコードに照らして、コンプライになるわけでもないでしょう。
そして、説得力のある「エクスプレイン」は、形式的な「コンプライ」よりも高く評価される可能性もあります。画一的な基準運用を行う投資家には評価されないかもしれませんが、すべての機関投資家が画一的な運用ではありませんので、自社の株主構成に応じて、しっかりと対話を行うことで理解を得られる場合もあるはずです。
最後に
議決権行使助言会社や機関投資家が推進する社外役員の「12年ルール」は、その表層的な画一性という点で疑問があるものの、取締役会の新陳代謝に関する規律の欠如や、役員個人のパフォーマンス評価が適切に運用・開示されていないという、日本企業が抱えるガバナンス上の課題もあり、在任期間基準の考え方について理解はできます。
しかしながら、これまでの検討の通り、議決権行使助言会社や機関投資家の形式的で一律の在任期間基準は、必ずしも取締役会の実効性を高めることに貢献するとは限りません。
外部から企業を評価するうえで分かりやすい指標ではありますが、企業内部の実務家目線では本質的でない基準だと感じるのも、やむを得ないのではないでしょうか。
企業が目指すべき最終的なゴールは、取締役会の実効性を高め、業績を伸長させることにあります(そのうえでの株主還元)。
繰り返しになりますが、このゴールを達成するためには、取締役会の構成と評価という二つのアプローチが決定的に重要です。
実効性が担保された取締役会の存在と企業価値向上という結果の前には、在任期間が何年かという議論は、きっと二次的な問題となっているはずです。