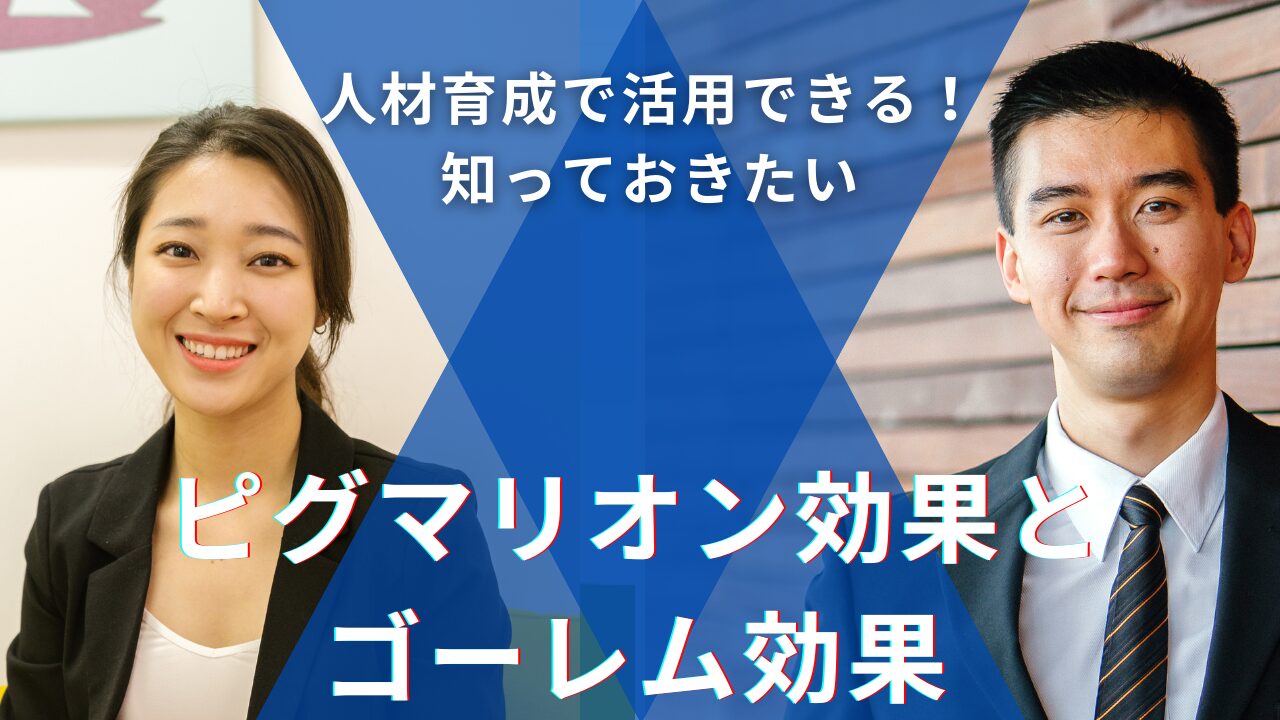1.はじめに
人材育成において、心理学は有効に活用されています。すでに意識せずに心理学を使っておられる方も多くおられると思いますが、知ることでより効果的に活用できます。
今回はビジネスにおける人材育成という文脈で知っておきたい「ピグマリオン効果」と「ゴーレム効果」についてご紹介します。
2. ピグマリオン効果とゴーレム効果とは
ピグマリオン効果
ピグマリオン効果とは、「期待をかけることで対象者のパフォーマンスが向上する」ポジティブな心理効果を指します。
この効果は、ギリシャ神話の彫刻家ピグマリオンの物語に由来し、教育現場におけるローゼンタールとジェイコブソンの研究によって広く知られるようになりました。
また、主観的な期待や思い込みであっても、結果的にそれが実現してしまう現象は、予言の自己実現(自己成就予言)と言われ、ピグマリオン効果は自己成就予言の一種とされます。
ピグマリオン効果は、期待を抱く側が対象者に対してより温かい態度を取り、より多くの情報や難しい課題を与え、より多くの発言機会を提供し、より多くの称賛や詳細なフィードバックを行うことによって生じます。
そして、期待を受けた個人は、他者からの肯定的な評価を内面化し、その期待に応えようと努力することで実際に成功を収める傾向があるとされます。
さらに、自己肯定感や自己期待を直接的に高めることでパフォーマンスが向上するガラテア効果も、ピグマリオン効果とともに、「期待」が持つ心理現象として語られることがあります。
ピグマリオン効果は単に高い期待を表明するだけでなく、指導者(教師や管理職)がその信念を言動で示すことが重要であり、これには、より難しい仕事を与える、建設的なフィードバックを提供する、励ますような肯定的な態度を示すなどが含まれます。
ゴーレム効果
ゴーレム効果は、ピグマリオン効果の逆で、「期待されない、あるいは低く評価されることで、対象者のパフォーマンスが低下する」ネガティブな心理効果を指します。
ゴーレム効果は、ユダヤの伝承に登場する、主人の命令によって動く泥人形「ゴーレム」に由来しています。ゴーレムは額に書かれた文字の一部を消されると、ただの泥に戻ってしまうとされており、他者の否定的な影響によって能力が失われる様子に例えられています。
例えば、低い期待を持つ管理職は、部下に対して支援を減らし、単調なタスクを与え、過度に管理する傾向があります。
ゴーレム効果も自己成就予言の一種であり、個人は否定的な評価を内面化し、モチベーションと努力を低下させ、結果として期待通りの低いパフォーマンスを示すようになります。
低い期待はパフォーマンスの低下を招き、それがさらに低い期待を強化するという悪循環に陥る可能性もあります。
ゴーレム効果は、明示的な否定的なコミュニケーションがなくても、管理職の無意識の偏見や先入観によって引き起こされる可能性があり、従業員がそれを察知することでパフォーマンスが低下することがあります。
3.人材育成におけるピグマリオン効果の活用方法
多くの企業では、OJTで人材を育成しています。例えば、先輩が後輩に期待をかけながらOJTを行うことで、ピグマリオン効果が発揮され、OJTの効果を高めることができると考えられます。
他にも、上司と部下の1on1ミーティングや考課者面談など、様々な場面を通じて期待を伝えることも有効です。
ピグマリオン効果の活用を企図した時に、このように期待を言語化して直接的に伝える方法はイメージしやすいと思います。ですが、企業の人材育成においてピグマリオン効果を活用する方法は多岐にわたります。
次で具体的にご紹介いたします。
上司が期待を明確に言葉で伝える
まず「期待しています」「君ならできる」といったポジティブなメッセージを直接伝えることが重要です。
このとき、ただ漠然と「期待している」だけでなく、具体的にどのような点に期待しているのか、どのような成長を望んでいるのかを明確に伝えることで、相手はその期待を認識し、それに応えようと努力するようになります。
例: 「このプロジェクトは、〇〇さんのこれまでの経験と△△の強みを活かせば、必ず成功させられると期待しているよ。」
適度な裁量と権限を与える
そして、単に言葉で期待を伝えるだけでなく、実際の業務において、部下に責任と権限を委譲することが有効です。
これにより、部下は「信頼されている」「任されている」と実感し、主体性を持って業務に取り組むようになります。
例: 「この仕事の進め方については、基本的な方針は伝えるが、具体的なプロセスや判断は〇〇さんに任せる。困ったらいつでも相談してほしい。」
例: 「貴方の判断で自由に試してほしい。予算も10万円まで、貴方の判断に任せます。」
少しストレッチした目標を与える
現在の能力より少し上の、達成可能だが努力が必要な目標を設定することで、成長を促すします。達成できた際には自信につながり、さらに高い目標へ意欲が湧きます。
例: 「今期は、新規顧客を△件獲得するという目標設定はどうだろう?前期実績を超えるチャレンジングな目標だけど、きっと貴方なら達成できると思う。」
ポジティブなフィードバックを積極的に行う
成果だけでなく、そこに至るまでのプロセスや努力も具体的に認め、褒めることで、相手のモチベーションを維持・向上させます。
例: 「今回のプレゼンは、資料作成に非常に工夫が見られたね。特に、データ分析の視点が素晴らしかった。おかげで顧客も納得してくれたよ。」
例: 「難しい課題だったにもかかわらず、粘り強く取り組んだ姿勢は本当に素晴らしい。その努力が次の成功につながるはずです。」
定期的なコミュニケーションと傾聴
1on1ミーティングなど定期的に部下と向き合う時間を設け、部下の個性や強み、現在の課題、キャリアプランなどを深く理解する努力をします。
部下の話を傾聴し、それに基づいて適切なアドバイスや支援を行うことで、信頼関係を築き、期待を伝えやすくなります。
例: 「1on1ミーティングを通じて、〇〇さんの今後のキャリアについて一緒に考えていきたい。何か困っていることや、挑戦したいことがあれば、遠慮なく話してほしい。」
失敗を成長の機会と捉え、再挑戦を促す
部下が失敗した際に、過度に叱責するのではなく、「失敗も成長の糧」と捉え、再挑戦を促す姿勢が重要です。
必要であれば、改善のためのヒントやサポートを提供し、見守ることで、部下は安心して挑戦できるようになります。
例: 「今回のミスは残念だったが、この経験から学べることがあると思う。次も貴方にお願いしたいので、どこが課題でどのように改善すれば次に活きるかを考えて、今回の経験を糧にしてほしい。」
OJTでの活用
OJTの指導者が、新入社員や後輩に対して「期待している」というメッセージを意識的に伝え、具体的な課題を与えることも有効です。これにより自律的な学習と成長を促します。
例: 「この業務は難易度が高いが、〇〇さんならできると思うので、ぜひ挑戦してほしい。わからないことがあればいつでも聞いてほしいし、私も適宜声をかけさせてもらう。」
評価制度と上司評価の公平性と透明性の確保
評価制度と上司評価が明確で公平であることは、期待をかける側の言葉に説得力を持たせます。
成果だけでなく、目標達成までのプロセスも評価対象にすることで、部下は努力が正当に評価されていると感じ、モチベーションを高く保つことができます。
注意点:過度な期待や無責任な期待は避ける
ピグマリオン効果は強力ですが、過度な期待はプレッシャーとなり、かえって逆効果になることがあります。また、根拠のない期待や、期待を伝えただけで丸投げするような無責任な態度は避け、状況に応じたサポートやフィードバックを継続的に行うことが重要です。
個人の能力や性格を考慮し、一人ひとりに合わせた「適度な期待」をかけることが成功のポイントになります。
4.避けるべきゴーレム効果
ゴーレム効果は、職場や教育現場など、様々な場面で起こり得ます。
上司の不信感や低評価
異動でAさんが配属された部署で、上司が「Aさんは前の部署でミスが多かったと聞いているから、あまり期待できないな」という先入観を持っているとします。そうすると、上司はAさんに対して、重要な仕事は任せず、簡単なルーティンワークばかりを割り当て、発言にも耳を傾けない、あるいは「どうせ無理だろう」といった態度を取ります。
その結果、Aさんは「自分は期待されていない」「信頼されていない」と感じ、モチベーションが著しく低下します。新しいことへの挑戦意欲がなくなり、自ら考えて行動することも減り、結果的に実際にパフォーマンスが低下したり、ミスが増えたりする悪循環に陥ります。上司のAさんに対する初期の低い評価が、現実のものとなってしまいます。
特定の社員への固定観念
長年同じ部署にいるBさんに対して、上司が「Bさんはいつも指示待ちで、自ら行動しない」という固定観念を持っているとします。そうすると、たとえBさんが新しい提案をしようとしても、「またどうせ無駄なことだろう」と真剣に聞こうとしなかったり、そもそも提案の機会すら与えなかったりします。
そうするとBさんはそれを察知し、「何を言っても無駄だ」「どうせ評価されない」と感じてしまいます。その結果、積極的に意見を出すことをやめ、言われたことしかしない「指示待ち人間」になってしまいます。
こうなると、もうBさんの成長は止まってしまいます。
ローゼンタールとジェイコブソンの実験
ローゼンタールとジェイコブソンが行った有名な実験では、ある教師に、ランダムに選ばれた生徒たちを「成績が伸び悩む可能性のある生徒」として提示しました。実際には、これらの生徒たちは他の生徒と能力に差はありませんでした。
教師は、これらの生徒たちに対して無意識のうちに期待をかけなくなり、接し方や指導の質が他の生徒と比べて低下しました。その結果、数ヶ月後には実際にこれらの生徒たちの成績が低下するという現象が見られました。
教師の低い期待が、生徒の実際の学業成績に悪影響を与えたのです。
人材育成におけるマイナス効果
人材育成においてゴーレム効果がもたらすマイナス効果は甚大です。
- モチベーションの低下
期待されていないと感じた社員は、仕事への意欲を失い、積極的に業務に取り組むことがなくなります。 - 自信喪失と自己肯定感の低下
低い評価を受け続けることで、自身の能力に疑問を持ち、自信をなくします。これが自己肯定感の低下につながり、新たな挑戦を避けるようになります。 - パフォーマンスの低下
モチベーションと自信の低下は、そのまま業務パフォーマンスの低下に直結します。本来持っている能力を発揮できなくなり、ミスが増えたり、成果が出にくくなったりします。 - 成長機会の損失
重要な仕事や挑戦的なプロジェクトを任されなくなるため、スキルアップや経験を積む機会が失われます。結果として、個人の成長が停滞し、キャリアパスも限定されてしまいます。 - ネガティブな組織文化の醸成
ゴーレム効果は、特定の個人だけでなく、部署やチーム全体に波及する可能性があります。上司や同僚からのネガティブな評価が蔓延すると、組織全体の士気が低下し、協力体制も損なわれる可能性があります。 - 離職率の増加
自身の成長が見込めない、あるいは正当に評価されていないと感じた社員は、最終的に会社を辞める選択をする可能性が高まります。人材の流出は、組織にとって大きな損失となります。(人材流動化の昨今、それが新陳代謝を生むという考え方もありますが、採用難易度が高い中小企業や中堅企業においては、仮にパフォーマンスが高くなくとも、ベテラン人材の退職が痛手であることは間違いないでしょう)
このように、ゴーレム効果は個人の成長を阻害するだけでなく、組織全体の生産性や士気に悪影響を与えるため、特に注意し意識的に避けるべき心理効果と言えます。
5.まとめ
ピグマリオン効果には懐疑的な見方もあるようですが、自分自身を振り返っていただくと、例えばこんなご経験はないでしょうか?
- 上司から、そんな声掛けをされたことがある
(あるいは、自分がしている) - 期待していると言われて、その期待に応えようとしたことがある
(あるいは、自分が言っている) - 現状に甘んじない程度の、少しストレッチした目標を与えられたことがある
(あるいは、自分が与えている)
これらに当てはまる経験をお持ちの方も多いと思います。
管理職の方はもちろん、後輩を指導する立場にある方にとって、ピグマリオン効果とゴーレム効果は知っておきたい心理効果です。
それぞれの特徴を理解し、方法論を組み合わせて、意識的に人材育成に活用いただければと思います。