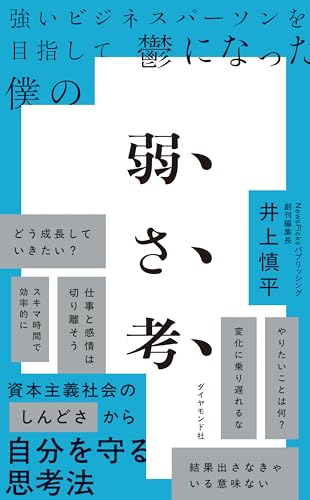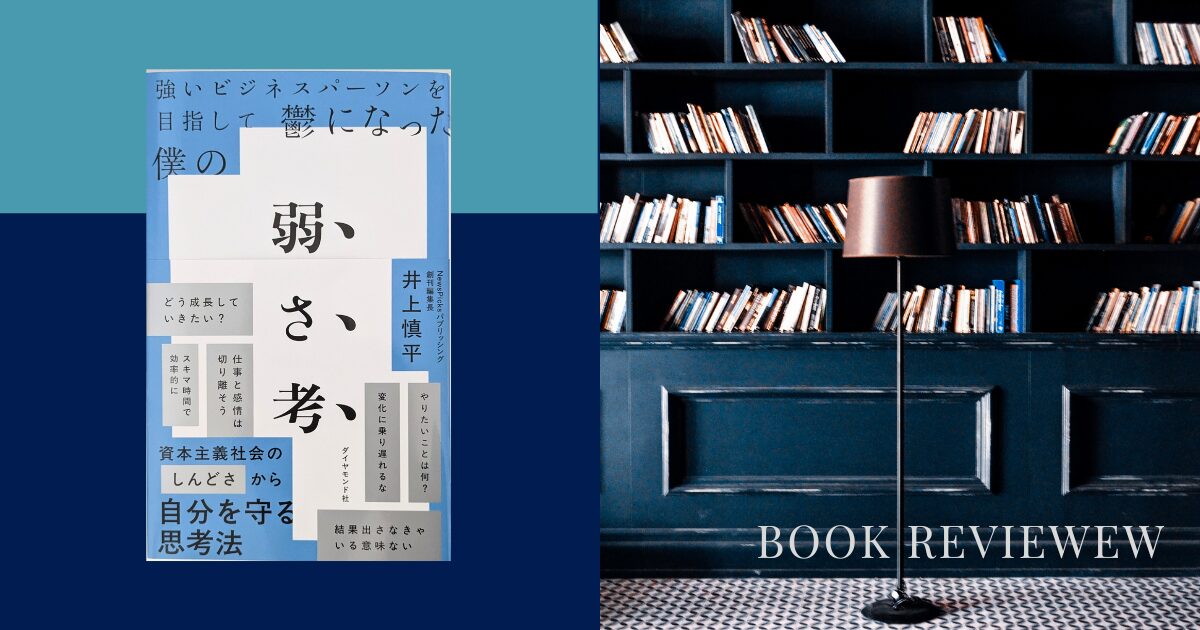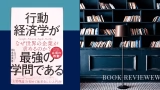本の概要
タイトル:弱さ考
著者等:井上慎平
出版社:ダイヤモンド社
あらすじ
本書は、現代社会における「強さ」の追求がもたらすプレッシャーや、そこでの「弱さ」との向き合い方を探る内容です。著者は、編集者としての経験や自身が双極性障害を発症した経験を通じて、「成長至上主義」や「能力主義」に対する疑問を提起し、「弱さ」を受け入れることで自分を守る思考法を提案しています。
著者自身の経験を交えながら、「ありのままの自分」を受け入れ、弱さと共生することで、より自由に生きる道筋を示す一冊です。
主要テーマ
- 成長至上主義への疑問
- 絶え間ない成長を求められる社会風潮の問題提起
- 競争原理を転換する必要性
- 弱さの再評価
- 弱さは克服すべきものではない
- 弱さを認めることで生まれる真の強さと豊かな人間関係
- 現代社会の問題点
- 時間の効率化へのプレッシャー
- 能力主義がもたらす格差と心理的負担
- 自己責任論の限界
- 実践的アドバイス
- 「課題の分離」による心理的負担の軽減
学びと共感
ポッドキャストでニュースコネクトという番組を聞いていたら、本書の著者である井上慎平氏がゲスト出演されていて、野村高文氏と軽快なトークを展開されていました。そこから興味を持って手にした一冊です。
弱さの定義
本書の中で、「弱さ」は次のように定義されており、この定義はすごくスッと自分の中に入ってきました。
規範を守り、「社会に求められる人間像」の幅(レンジ)に自分をコントロールすることができる人は強く、それができない人は「弱い」。自己コントロールは現代に始まったことじゃないが、現代はその難易度が一気に上がっている。
感情の水風船はパンパンに膨らんで破裂した。でもなぜ、破裂するまで僕はその存在にすら気づかなかったのだろう。何から必死に眼を逸らし続けていたのだろう。きっと僕は「何もできない自分になった」ことだけは、絶対に認めたくなかったのだ。
いきすぎたネガティブ思考自体がうつの典型的な症状だ。それも知識としては知っていた。だが、思考をコントロールできない。
最近知ったのだが、物理的に「痛い」ときに活性化する脳の部位と、言葉で傷つくなど「こころが痛い」ときに活性化する部位は同じらしい。
いずれも双極性障害を持つ筆者だからこその生々しい表現です。自身の葛藤・惨めさ・口惜しさなど、とても複雑な感情がないまぜになっている印象を受けました。読んでいてぐっと迫るものがありました。
著者の考えを自分なりに解釈して、自分自身はどうなのか?と思惑を巡らせてみます。
厄介なのは「社会に求められる人間像」は変化するということでしょう。つまり「社会に求められる人間像」のレンジの中に自分をコントロールするためには、自分自身が一定でいられず、常に適応していかねばならない点にしんどさや難しさがあるように思えます。
自分の個性を起点にして適応しやすい方向に求められる人間像が変化する場合の適応は容易ですが、適応しにくい方向への変化だと途端に適応の難易度が上がります。人間はそれほど器用にできていませんよね。
これを仕事に引き付けて考えると、全ての令和の世にあって平気でセクハラ発言をする人、未だに長時間労働や皆勤を美徳と考える人なども「弱い」と区分できるでしょう。
他にも、受動喫煙防止・健康増進のために法整備・条例が整備されているにもかかわらず、未だに歩きたばこを辞められなかったり路上喫煙をしている方も、「社会に求められる人間像」のレンジに自分をコントロールできていないので「弱い」といえそうです。
では、弱さと表裏一体で、強い人も気が付くと弱くなっている可能性がある現代において、どのようにすれば「社会に求められる人間像」のレンジに自分をコントロールし強い自分であり続けることができるでしょうか?
私にとっての解は「演じる」ことです。
弱さを受け入れる「社会から求められる人間像」を自分の役割だと思って、演じていくと、初めは居心地の悪さがありますが、時間の経過とともに自分の個性に溶け込んでいきます。溶け込まず、自分と相いれない社会の変化があったとしても、それを役割として演じることができれば、レンジの中に収まった振る舞いが可能です。
弱さをそのまま受け入れるという著者の主張とは異なりますが、これもある種の自己防御だろうと思います。役割という“鎧”をまとうことで、自分の心を守っていると言い換えることができるかもしれません。
そんな鎧をまとっているからこそ、人事の責任者として諸案件の対応ができるのだろうと考えています。 大きなストレスと背中合わせの仕事をされている方には、似た考えをお持ちの方がおられるかもしれません。ただ大小問わず、どんな仕事でもストレスは存在します。ストレスがない世界など存在しないと思います。
例えば、同じ組織に属していて会社を良くする・業績を上げるという根っこは同じでも、人によってそのアプローチは異なります。部門や立場によって重視すべきポイントも異なったりします。その時々で「自分が求められる(果たすべき)役割は何か?」を考え、ある意味どこか役者になったような感覚で、その役割を演じることができれば、ある程度までは自分の心を守るように思います。
自分自身もある程度は変化しますが、積極的に「社会から求められる人間像」に合わせていくのは、求められる人間像を演じる役者の自分です。
こうすることで「社会から求められる人間像」が変わっても、それは演じる役割が変わったと捉えて、自分自身を大きく変化させずに、求められる役割を演じることができます。完全ではないにしても、自分の考えと求められる役割を切り分けることで、自分という存在が変化しつつも、一方では自分らしくあり続けることができるように思います(こう書くと二重人格っぽいですがw)。
「弱さ考」を読んで、我が身を振り返る良いきっかけになりました。
メンタル疾患は、現代のビジネスパーソンに共通する悩みだろうと思います。著者の考えを知るだけでなく、読みながらとても考えさせられる一冊でした。おすすめです!