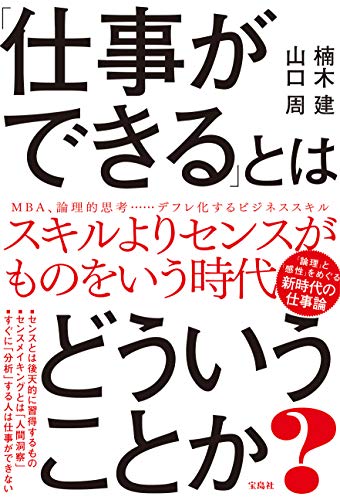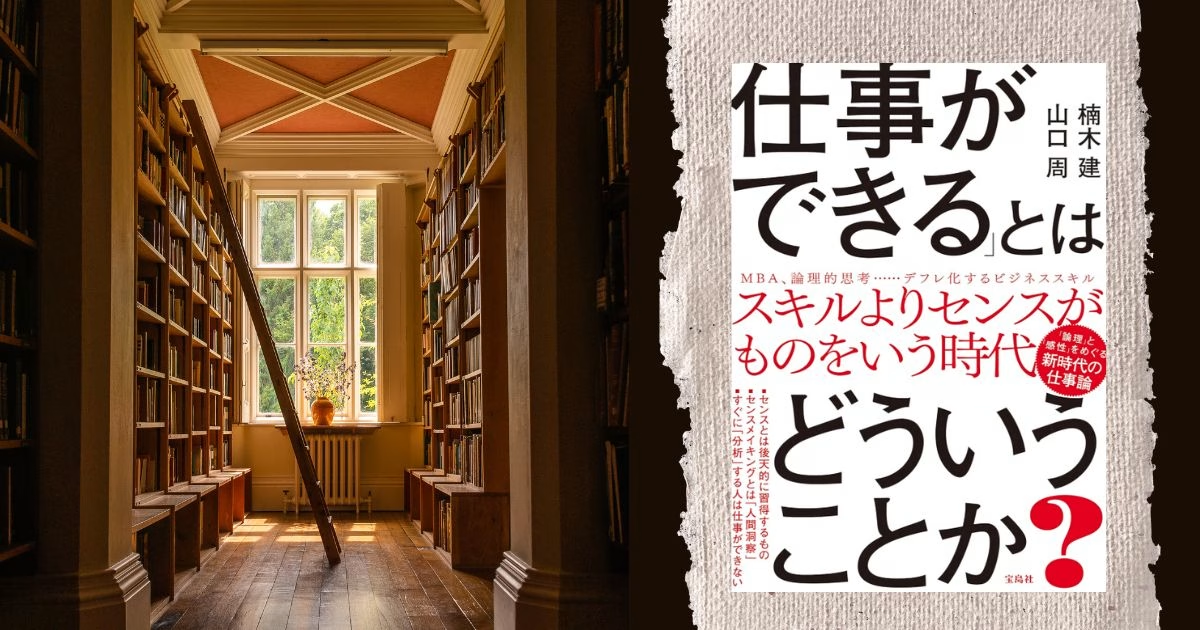概要
📖 タイトル:仕事ができるとはどういうことか
🤵 著者等:楠木健、山口周
🏢 出版社:宝島社
目次
はじめに 楠木 建
第1章スキル優先、センス劣後の理由
アート派、センス派は“ビルの谷間のラーメン屋”
ビジネスとは問題解決
「役に立つ」はスキル、「意味がある」はセンス
問題は解決すればするほ「量」から「質」にシフトする
「論理」は常に「直観」を必要とする
センスの劣後と日本人の「因果応報」世界観
“直観主義”小林秀雄は批判され、“努力の人”矢吹丈は愛された
弱い人ほど「法則」を求める
「好き嫌い」の問題を「良し悪し」へ強制翻訳
センスにも「序列」をつけたがる日本人
「アスリート型ビジネス」と「アート型ビジネス」
日本でアスリート型ビジネスが優位だった理由
男のマウンティングは「スキル」に収斂する
人事における「コンピテンシー」という概念の誕生
第2章「仕事ができる」とはどういうことか
労働市場で平均点にお金を払う人はいない
「やってみないとわからない」センスの事後性
勝間和代がブームになった理由
400メートルハードル・為末大に見る「身の置き場所」問題
ユニクロ・柳井正が己の才能に気づいた瞬間
「AC/DC」に見るセンスの不可逆性
センスがない人が出世する組織の不幸
すぐに「分析」する人は仕事ができない
カルロス・ゴーンの勘所
「担当者」と「経営者」の仕事の違い
小林一三とチャーチルのセンス
どこで勝負するかという「土俵感」
センスと意欲のマトリックス
プロのすごみは、やることの「順序」に表れる
原田泳幸の〝アートな〞マクドナルド立て直し
第3章何がセンスを殺すのか
ビジネスパーソンの「エネルギー保存の法則」
「横串おじさん」と位置エネルギーの“魔力”
センスのある人の「仕事は仕事」という割り切り
エリートはなぜ「階層上昇ゲーム」が好きなのか
「ビンタしてから抱きしめる」と「抱きしめてからビンタする」の大きな違い
センスある経営者は「『それでだ』おじさん」
「独自のストーリー」があるから同じものが違って見える
「これからはサブスクだ!」が見落としているもの
元祖“センス派”カール・ワイクの究極セッション
最旬ビジネスワードという“飛び道具”の誘惑
「インサイド・アウト」か「アウトサイド・イン」か
「ネットフリックス」強さの淵源
環境や状況に原因を求める「気象予報士」ビジネスパーソン
「誰か俺を止めてくれ」究極のインサイド・アウト
アムンセンとスコットの違い
第4章センスを磨く
センスの怖さはフィードバックがかからない点
島田紳助の「芸人は努力するな」の意味
「修行」というセンス錬成法
センスとは後天的に習得するもの
ジャパニーズ・ロストアート
日本電産・永守重信の人心掌握力
センスメイキングとは「人間洞察」
データでは見えない人間の「矛盾」
一流の人は「自分が小さい」
センスとは「具体と抽象の往復運動」
「根本的矛盾」を直視する
「抽象的思考」は難しいけど面白い
抽象的な理解ほど実用的で実践的なものはない
どうやって自分の土俵を見極めるか
仕事ができる人は自分の「意志」が先にくる
仕事ができない人の「過剰在庫」
おわりに 山口周
💡 印象に残った論点
1. 「スキル」の出発点に不可欠な「直観」
一般に「仕事ができる」というと、ロジカルシンキングや特定の専門知識といった「スキル」が重視されます。しかし本書は、その論理的な思考をどこからスタートさせるか、すなわち「問題を発見・設定する」という最初の段階において、直観(センス)が不可欠であると指摘しています。
「このあたりが本質的な問題のキモではないか」とアタリをつける作業は、データ分析以前の、個人の嗅覚に依存するからです。
2. スキルでは説明できない成功要因「コンピテンシー」
成功要因を知識や学歴といった既存の指標に求めても、現実のパフォーマンスと統計的な相関がないという衝撃的な事例が紹介されます。特にアメリカ外務省の外交官の選抜事例は象徴的です。超一流の学歴や語学力、交渉術といった「スキル」は必要条件ではあっても、赴任先での成功を保証する「十分条件」ではないのです。
”学歴が高い=仕事ができるわけではない”ということは、まさに経営者や人事の皆さんも感じておられることかと思います(その蓋然性が高いとは思いますが、明確な相関がない)。
この「スキルでは測れない成功要因」こそが「コンピテンシー」と名付けられました。成功した外交官に共通して見られた行動・思考パターンは以下の3点に集約されます。
- 高い対人感受性
相手の文化や背景が異なっても、その人が今何に悩み、何に怒っているかを鋭く察知する能力。 - 建設的な関係構築への思考パターン
人種や宗教の違いに関わらず、「最終的には信頼関係を築けるはずだ」という、根源的な人間への信頼を持つフラットな姿勢。 - 政治的な力学に対する嗅覚
組織図上の役職者ではなく、文化大臣の奥さんの愛人など、非公式な意思決定上のキーマン(フィクサー)を見抜く力。
知識やスキルではなく、「ものの見方」や「対人姿勢」というコンピテンシーが、本当に「仕事ができる」人に共通する特性で、これが今、人事においてコンピテンシーが一般化したことにつながっているのです。
3. センス育成の「事後性」
センスの育成はキャリア構築の実態そのものですが、その特性として「事後性が高い」ことが挙げられています。スキル学習のように費用対効果や因果関係を事前に明確にできず、様々な経験を一通り積み、「今」の自分を振り返ってみて初めて、過去のどの経験が今の自分のスタイルやセンスを形作ったのかが分かるという点です。
🛠 実務への示唆
1. センスを磨くための「具体」と「抽象」の往復
センスは生まれつきのものではなく、鍛えることができます。そのためのカギとなるのが、「具体」と「抽象」の思考の往復です。
目の前の具体的な事象(自分の経験、ニュース、景色)を材料とし、「だから今、こういうことが起こっているのではないか?」「これからこういう時代が来るのではないか?」という抽象的な問いを立て、それに対する意見を考え、発信することでセンスは鍛えられます。
例えば課長職など組織の要となる立場では、今の組織の具体的な問題から、「これからの人事はどうあるべきか?」といった抽象的な提言を導き出し、実行していくことで鍛えることができます。
2. 自分の「センスの土俵」を理解する
成功者であっても、あらゆる局面にセンスを発揮できるわけではありません。日産のゴーン氏がリストラフェーズでは優秀でしたが、競争力構築フェーズでは力を発揮できなかった例や、小林一三氏が銀行で苦しみ、鉄道事業で才能を開花させた例が示すように、成功者は自分のセンスが機能する「土俵(コンテクスト)」をよく理解しています。
実務において、自身の強みとなるセンスがどの領域で最大限に活かせるのかを見極め、戦う場を選ぶことが、キャリア選択の鍵となります。
3. 「全体」を統合するセンスこそが本質
本書は、スキルはあくまで「部分」であり、いくらスキルを磨いても「全体」が良くなるとは限らないと説いています。組織における弱点を見抜き、時流に合わせて改編していくためには、部分が分断されることなく、「全体」をストーリーとして統合的に捉えるセンスが不可欠という主張です。
この統合力は、組織を俯瞰的に見つめ直す姿勢から生まれます。大人物ほど自分を客観視するために「自分を小さく考える」という指摘は、人の立場で物事を考え、「全体」の弱点を的確につかみ取るための謙虚な姿勢の重要性を示しています。
📝 総評
本書は、「なぜかあの人はうまくいく」という疑問に対し、学問的な知見と豊富な実例(外交官、有名経営者)で掘り下げています。
特に、若手社員へのアドバイスとして紹介された「常に機嫌よく挨拶する」「仕事ができる人を観察する」「顧客の視点で考える」という3点は、コンピテンシーの土台となる姿勢は、誰でも実践できるアドバイスで。
部分から全体をイメージできること、そして「全体」を良くするための「統合」ができるか、「部分」が分断されず、「全体」をストーリーとしてつなげて思考できることが「センス」の正体です。
仕事ができるとはどういうことか?仕事ができる人はどういう人か?を考えるビジネスパーソン必読の一冊としてお勧めいたします。